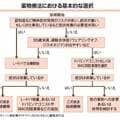レビー小体は、パーキンソン病の進行に伴い黒質以外の大脳皮質にまで広がり、認知機能の低下を起こすことがあり、パーキンソン病の人は、そうでない人に比べ認知症を起こしやすいとされます。
レビー小体が神経細胞にたまる病気には「レビー小体型認知症」もあります。この場合、パーキンソン病と違って、レビー小体は最初から大脳皮質にたまります。レビー小体型認知症の特徴は、認知機能の低下に加え、幻覚・妄想、そしてパーキンソン病と同様の運動症状が起こることです。
「パーキンソン病とレビー小体型認知症は、兄弟のような病気と言えるでしょう。今のところ両者の区別は、認知機能の低下が運動症状と同時もしくは1年以内に起こった場合はレビー小体型認知症、運動症状より1年以上遅れて認知機能の低下が起こった場合はパーキンソン病に伴う認知症とされています」(大山医師)
発症の仕組みが徐々にわかってくることで、病気の根本にアプローチする研究も進んでいます。例えば、血液中からα-シヌクレインに関わる物質を検出することに成功しており、運動症状が表れる前にパーキンソン病の前兆をとらえる血液検査や、α-シヌクレインを取り除くような治療の開発につながるものと期待されています。
足を引きずる、表情が乏しくあまり活動しなくなったなど、気づいた症状によっては、最初に整形外科や精神科を受診する人もいます。その後、脳神経内科に紹介されることもありますが、しばらくパーキンソン病だと気づかれず診断が遅れることもあります。
「パーキンソン病は早期に発見して早期に適切な治療を開始することが大切です。また、パーキンソン病とよく似た症状で始まるほかの脳変性疾患もあるため、よく区別しておくことが必要です。それらしい症状があれば、ためらわずに脳神経内科にご相談ください。日本神経学会のホームページを見ていただくと、神経内科の専門医や主要な病院を探すことができます」(大江田医師)
(文/山本七枝子)
【取材した医師】
順天堂大学順天堂医院 脳神経内科 准教授 大山彦光医師
2002年、埼玉医科大学医学部卒。10年、順天堂大学医学研究科で博士号取得。米フロリダ大学Movement Disorder Center フェロー等を経て、14年4月から現職。脳深部刺激療法(DBS)治療のチームリーダーを務めるほか、遠隔地にいる患者の体の動きを3次元でとらえる3次元オンライン診療システムの開発にも携わる。患者会(パーキンソン病友の会)のイベントに参加するなど、患者との交流にも力を入れている。
順天堂大学順天堂医院:東京都文京区本郷3-1-3

国立病院機構宇多野病院 臨床研究部長/京都大学医学部 臨床教授 大江田知子医師
1993年、大阪市立大学医学部卒。2003年、京都大学大学院で博士号取得。01年から国立病院機構宇多野病院脳神経内科。脳神経内科医長を経て、16年から現職。診断から進行期にいたるまで、パーキンソン病を中心とした脳変性疾患の診療に携わり、「最適な治療は患者さんを知ることから」をモットーにコミュニケーションを大切にしている。専門医の少ない地域での保健所による個別医療相談にも取り組む。
国立病院機構宇多野病院:京都市右京区鳴滝音戸山町8

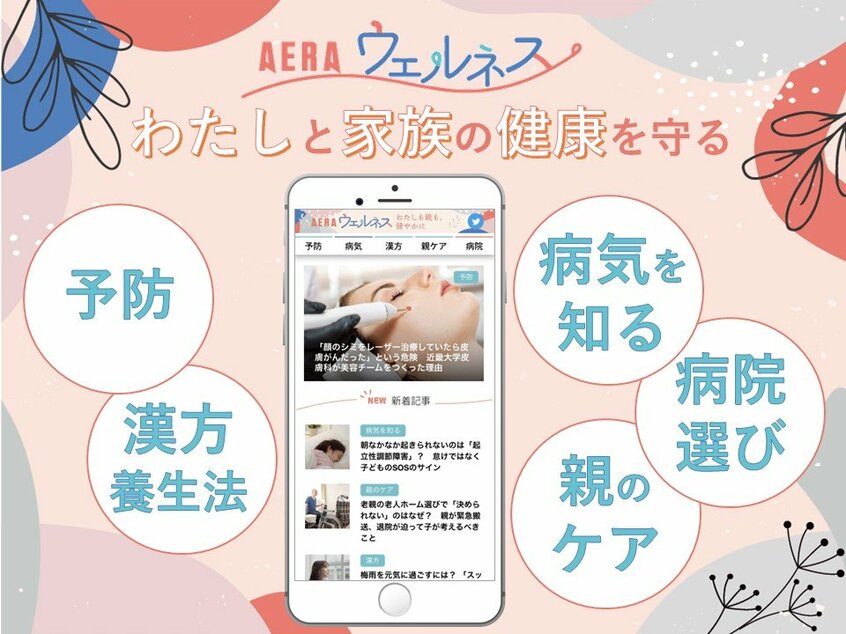
連載「名医に聞く 病気の予防と治し方」を含む、予防や健康・医療、介護の記事は、WEBサイト「AERAウェルネス」で、まとめてご覧いただけます。
こちらの記事もおすすめ 【パーキンソン病】薬では進行を止められない 症状を抑えられなくなったら手術を検討