「そのような子どもたちには、食物経口負荷試験で食べられる量をきっちりと設定し、食べ続けることで症状が出なくなるように誘導していく方法があります。原因となる食物を、食べても大丈夫な量食べ続けることで結果的に食べられるようになるのですが、これを経口免疫寛容(けいこうめんえきかんよう)と言います。定期的に食物経口負荷試験をおこなって症状が出るかどうかを確認し、症状が出なくなれば治ったということになります」(手塚医師)
この方法は、食物経口負荷試験をおこなっている病院の多くで実施されています。
研究的な取り組み、経口免疫療法
基本的には治す方法がない食物アレルギーですが、近年、重症な食物アレルギー患者を対象に、非常に少ない量から食べ始めて少しずつ分量を増やし、結果として飲める量、食べられる量を増やそうという取り組みがおこなわれています。これは経口免疫療法という方法で、大学病院や子ども専門病院など特定の医療機関でのみおこなわれます。
「経口免疫療法はまだ研究段階の取り組みなので、原則的には特定の病院でしかおこなうことができません。うまくやれば非常に効果的な方法ですが、一歩間違えればアナフィラキシーなどを起こすリスクにもなります。そのため、食物経口負荷試験での微妙な分量設定や、経験のある専門医による的確な指示など、慎重におこなう必要があります」(今井医師)
ショック症状が出たら即座に救急車を!
食物アレルギーは子どもだけでなく、今までさまざまな食べ物を食べているはずの成人でも、突然になることがあります。近年はクルミなど木の実類のアレルギーも増えており、知らずに原因となる食物を食べてしまうこともないとは言えません。食物アレルギーは、特に外食や中食の場合、どんなに注意していても完全に避けることは難しいという認識を持つことが必要です。
「危険な症状を知っておくことが非常に重要です。飲食のあと、ふらふらする、血圧が下がっている感じがする、悪寒がする、息が苦しいなどの症状があったら、その場を動かず、即座に救急車を呼んでください」(手塚医師)
その症状が食物アレルギーかどうか、何を食べたかなどはあとで考えればよいこと。ショック症状が出たら、まずは命を守るために救急車を呼ぶ、ということを、肝に銘じておくことが大切です。
(取材・文/梶葉子)
【取材した医師】
昭和大学病院 小児科教授 今井孝成(いまい・たかのり)医師
1996年東京慈恵会医科大学医学部卒業、昭和大学医学部小児科学講座入局。独立行政法人国立病院機構相模原病院小児科医長を経て、2012年昭和大学医学部小児科学講座講師、18年同准教授、19年から現職。日本小児科学会、日本アレルギー学会、日本小児アレルギー学会などで理事を歴任。「食物アレルギー診療ガイドライン2021」などの作成に中心的に携わり、行政、教育機関などへの食物アレルギーの啓発、各自治体の食物アレルギー情報発信などに尽力。

福岡市立子ども病院 アレルギー・呼吸器科科長、こどもアレルギーセンターセンター長 手塚純一郎(てづか・じゅんいちろう)医師
1998年九州大学医学部卒業、九州大学病院小児科入局。九州大学病院小児科、独立行政法人国立病院機構福岡病院小児科、国立病院機構福岡東医療センター小児科医長を経て、2015年から現職。日本アレルギー学会、日本小児呼吸器学会、日本小児アレルギー学会、日本小児臨床アレルギー学会などで理事を歴任。食物アレルギーをはじめとするアレルギー疾患の啓蒙や、アレルギーの患者や家族に関わる多職種の連携推進に精力的に活動。

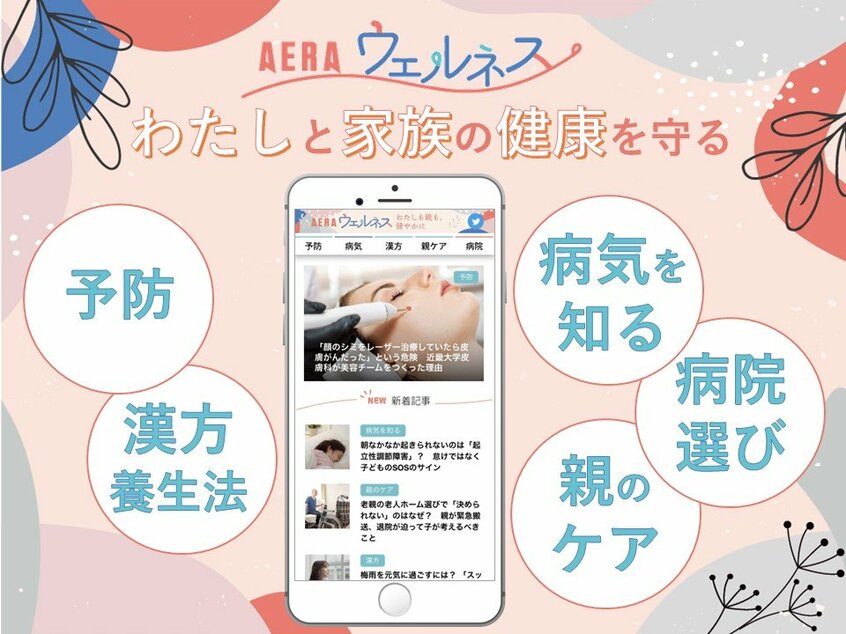
連載「名医に聞く 病気の予防と治し方」を含む、予防や健康・医療、介護の記事は、WEBサイト「AERAウェルネス」で、まとめてご覧いただけます
こちらの記事もおすすめ 子どものクルミアレルギー急増 食物アレルギー原因3位に 表示義務化も医師「中食・外食には注意」





































