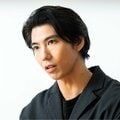かわいい子だからこそ、旅をさせたくない。近年、そんな親が増えていると指摘するのは、東京未来大学こども心理学部教授で『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉』著者の出口保行(やすゆき)さん。少子化が深刻になり始めた1990年代後半ごろから、「転ばぬ先のつえ」を用意する親が目立つようになった。
かつては、過保護といえば経済的に豊かな家庭での教育方針で、人手も資金も足りない「普通の家庭」にとっては縁遠い言葉だった。それが、少子化により加速したという。
「何をするにも親や周りが手助けしてくれるから、失敗しない。親が先回りできるうちはいいけど、大人になったらそうはいかない。経験値がないから、心が転んでしまったときに立ち上がる回復力が非常に弱くなってしまう」(出口さん)
問題なのは、回復力がないことだけではない。原因を究明する力が養われなければ、同じ失敗を繰り返してしまう。その過程で自信を失う悪循環に陥ることもある。
もちろん、命に関わるようなことは親が先回りして、止める必要がある。だが、小さな失敗の芽まで摘み取るケースが多いという。出口さんは言う。
「ランドセルの点検をする親なんて、いくらでもいる。子どもにしてみれば忘れ物をしないですむからそのときは助かる。だけど、自分で確認する癖がないから、社会に出たときに自己チェックできない。親が子どもの経験を奪っている」
(編集部・福井しほ)
※AERA 2023年7月17日号より抜粋