

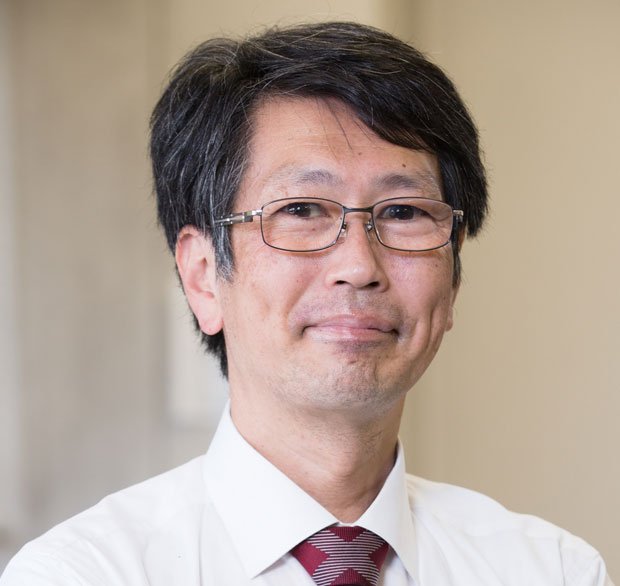
人気集中で難化する私大は、普通の学びを提供するだけでは生き残れない時代になった。独自性が自慢の私大を調査した。
東京理科大学は、「スペース・コロニー研究センター」を開設した。スペース・コロニーとは、宇宙空間の人工居住地のこと。ここで行われる宇宙滞在技術の研究は、文部科学省により「私立大学研究ブランディング事業」として認定されている。
木村真一教授の研究室では、地上の民生用デバイス(一般の人が使う家電の周辺部品)を活用した宇宙ゴミの除去技術に取り組んでいる。木村教授は言う。
「宇宙ゴミは弾丸の10倍の速さで地球の周りを回っており、接触を起こすと爆発する恐れがある。将来人間が月や火星に安全に行くためにも、ゴミを取り除くことが必須課題なのです」
地球からゴミを観測すると数キロもの誤差が生じてしまい、正確な位置をつかむことは難しい。木村教授が構想したのは、ゴミを見つけるカメラ、捕まえる手の役割を果たすロボット、これら一連の作業を制御する賢い計算機の開発だった。
「宇宙で使うカメラや計算機は、大きくて性能も低いうえに高価。ならば家電に使う半導体部品はどうか、と。大量に生産されているぶん値段が安いので、これらを改良することで、コスト削減を図りました」
放射線の照射や温度実験など宇宙環境を想定した耐久性テストを繰り返す。
「壊れない機器をゼロから作ろうとすると、莫大なコストがかかるので、厳しい環境に耐えられる部品をうまく利用する。誤作動が起こったら、それを修正する仕組みを作ればリスクは軽減されます」
修士課程1年の3人の学生も、この研究に参加している。竹原康太さんは宇宙ゴミに安全に接近するための制御技術を、堀玲郎(れお)さんはカメラが取得した画像を効率よく計算機に送る回路作りを、田村尚子さんは、カメラのレンズをガラスからプラスチックに転用する研究を担当。
「自分の作った物が衛星に搭載され、実際に宇宙で活用されるなんて、考えただけで胸が躍ります」(堀さん)
木村教授は、研究に携わることは教育効果が高いという。
「実際に搭載される製品を作るので、モチベーションが違います。課題が山のようにあるので、常に自分で問題を解決する習慣が身についている。これは社会に出てからも役立つと思う」
2010年5月に宇宙へ打ち上げられ、今も宇宙空間を飛んでいる宇宙ヨット「イカロス」に世界最小のカメラを搭載し、人類史上初めての衛星の“自撮り”に成功した。カメラにスピンをかけて衛星から放つと、重力の関係でくるくると回転する。衛星から遠ざかる数秒間に、50枚ほど激写したという。
数年以内には木村教授が技術提供しているアストロスケール社(シンガポール)が、宇宙ゴミの除去の実現に向けた技術実証衛星を打ち上げる予定だ。宇宙飛行士の向井千秋特任副学長は言う。
「日本の宇宙滞在技術は世界第3位で、潜在能力は高い。縦割りにやっている本学の研究をつなげば、さらにワクワクするようなすごい技術が生まれると思います」
(ライター・柿崎明子)
※AERA 2018年4月23日号より抜粋







































