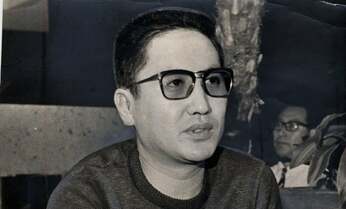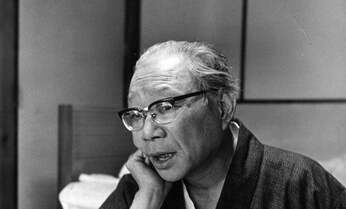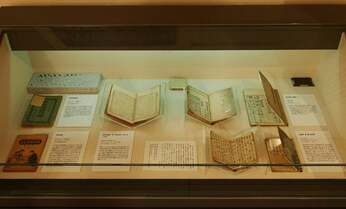
「歴史」に関する記事一覧
特集special feature


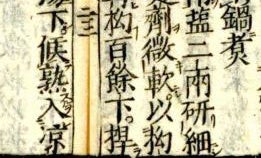

ロケ地でも人気 東京湾唯一の無人島「猿島」の魅力
東京湾は、品川から見ると対岸ははるか向こうで、広大な海と感じられるが、湾の入り口である浦賀水道の一番狭い場所は対岸まで7キロほどの距離しかない。このため、日本武尊の東征神話の時代からこの場所は、三浦半島と房総半島を結ぶ交通の要衝として知られてきた。今でもこの部分は国道16号線の環状線の一部、通行不能ではあるが海上道路として登録されている。もちろん東京へ海から上陸するには、この狭隘(きょうあい)な海峡を通過するしかなく、明治時代には国防の観点から海堡(かいほう)が築かれ、船の侵入をますます困難にした場所だ。この防衛線の一端を担っていたのが、横須賀沖の猿島である。