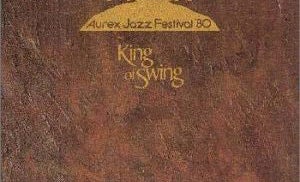
第42回 『オーレックス・ジャズ・フェスティヴァル'80ライヴ~キング・オブ・スイング』
『Aurex Jazz Festival '80 - King of Swing 』
第1回オーレックス・ジャズ・フェスティヴァルの目玉はベニー・グッドマンの尊称をプログラム名にした「キング・オブ・スイング」だったが、出来そのものも一番だった。既に71歳、多くが「観ることに意義がある」てな気分で足を運んだのかもしれないが、熱きスイング魂は瞬く間に会場を埋め尽くす老若男女の心をとらえ万雷の喝采を浴びた。足を運ばずNHKで放映された武道館でのライヴを観て地団太を踏んだ方もあるのでは。
大御所の来日は1957年1月、64年2月に続く三度目で、これが最後ともなった。最初はビッグバンドを、二度目はワンホーン・カルテット(この時に残した名盤は連載の第6回で紹介した)を、この度は3管セプテットを率いての来日だ。プログラムの目玉がもう一人いる。ジャズ・ピアノ史上の巨人、テディ・ウィルソンだ。昔のボスとの共演は8年ぶりだった。サイドマンは西海岸の中堅が並ぶ。トニー・テラン(トランペット)は名うてのセッションマン、ディック・ナッシュ(トロンボーン)は主にスイング系ビッグバンド畑の腕利き、サンフランシスコ人脈で共演歴もあるエディ・デュラン(ギター)、アル・オビデンスキー(ベース)、ジョン・マーカム(ドラムス)の3人はコンボ畑で、マーカムは1959~60年に御大のビッグバンド/コンボに在籍してもいた。この他、ツアーに先立ち御大が見出した女性コーラス・グループ「レア・シルク」が華をそえる。
放送映像(YouTubeで観られる)によると実際のステージもこの順に運ばれたようだ。クインテットでスタート、やがてブラス陣が加わり、中盤で「レア・シルク」を迎える。 幕開けは《アヴァロン》だ。御大が吹き始めるやいなや「観ることに意義がある」なんて予防線は吹き飛んだにちがいない。熱く一気呵成に吹き抜け、初っ端からウルっときた。テディも当夜のジェントルメン・オブ・スイングのステージとは一変し、闊達な好ソロを披露する。堅実でタイトなリズム隊も嬉しい。バラード《身も心も》では徒な感情移入を排した瑞々しい情感にうっとり。《レディ・ビー・グッド》では淀みない歌心で快走し、《世界は日の出を待っている》では熱くテクニカルに畳みかけて場を圧倒する。ここからブラス陣が合流する《ザッツ・ア・プレンティ》は場違いなディキシー・スタイルだが、ナッシュ、テラン、テディ、御大の好ソロが連続する、賑やかで楽しい聴き物になった。
ここで3人のオネエさん達が登場。何々シスターズの流れを汲むレトロ・グループだ。《ブロードウェイ》に《グディ・グディ》、観る分には華にせよ聴く分には魅力に乏しい。前者で3ホーン、後者で御大のソロをスポットする。《その手はないよ》はテーマのみ、《サヴォイでストンプ》に滑り込む。御大はテーマくらいで、ナッシュとテディのソロはまずまず。《エア・メイル・スペシャル》では「レア・シルク」がスキャットで加わる。御大、テディ、ナッシュのソロは平凡。バラード《あなたの想い出》はクインテットで。御大とテディが歌の精髄を描き出す、胸に迫る佳演だ。《シング、シング、シング》では意表を突いて「レア・シルク」が前面に立つ。ナッシュと御大のソロはピリっとしない。《スウィート・ジョージア・ブラウン》ではテディと丁々発止を演じ健気に吹き終える。《グッドバイ》はテーマ8小節に続いて御大が謝辞、ハッピーなステージの幕を降ろす。
終盤が今一つなのは、疲れがたまった後日録音のせいもあるだろう。初日の武道館では最後まで元気一杯で、《シング》ではテランがクリーンでシャープな快演を見せもする。それだけでまとめて欲しかった。それにしても武道館での御大には驚く。71歳とくれば口周りの筋肉も心肺も衰えていたはずだが、厄介な楽器と見事に一体化、精進の賜だな。これまた入手難で、リンク先ではバブリーな価格が付いている。LPを探すのが得策だ。[次回8月4日(月)更新予定]
【収録曲一覧】
Aurex Jazz Festival '80 - King of Swing (Jp-Somethin'else Classics [Jp-East World])
1. Avalon 2. Body And Soul 3. Oh, Lady Be Good 4. The World Is Waiting for the Sunrise 5. That's a Plenty 6. Broadway 7. Goody Goody 8. Don't Be That Way - Stompin' at the Savoy 9. Air Mail Special 10. Memories of You 11. Sing, Sing, Sing 12. Sweet Georgia Brown 13. Goodbye
Benny Goodman (cl), Teddy Wilson (p), Eddie Duran (g), Al Obidenski (b), John Markham (ds), Tony Terran (tp on 5-9, 11-13), Dick Nash (tb on 5-9, 11-13), Rare Silk: Mary Lynn Gillaspie, Gayle Gillaspie, Marguerite Juenemann (chorus on 6, 7, 9, 11).
Tracks 1-8, 10: Recorded at Budokan, Tokyo, September 3, 1980.
Tracks 9, 12: Recorded at Expo Park, Osaka, September 6, 1980.
Tracks 11, 13: Recorded at Yokohama Stadium, Yokohama, September 7, 1980.
※このコンテンツはjazz streetからの継続になります。

















