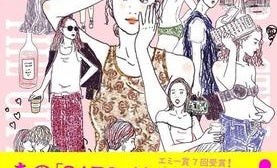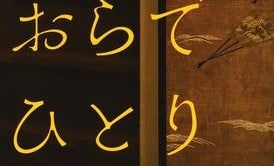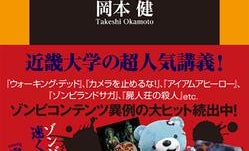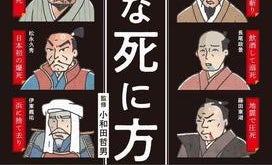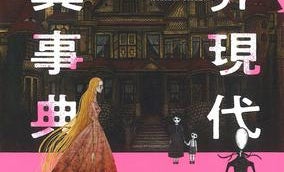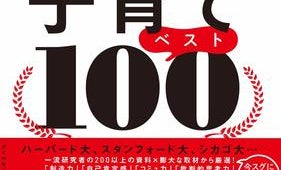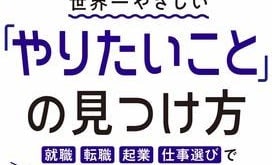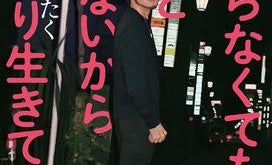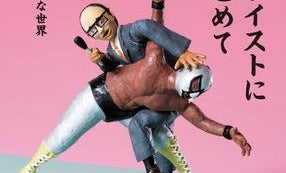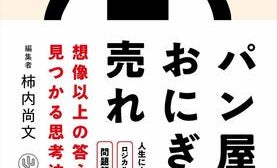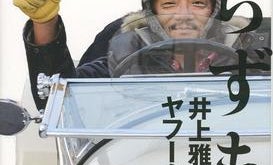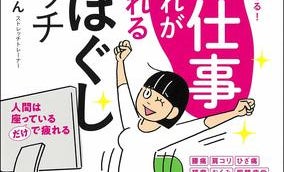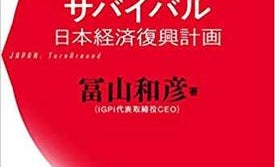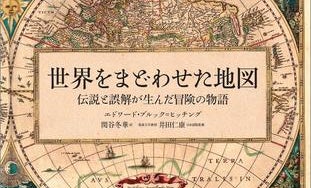『この世界の片隅に』のもとになった写真も 戦前・戦後の白黒写真をAIと人の手でカラー化
日本でカラー写真が普及したのは戦後のこと。それまではもっぱら白黒写真が一般的でした。白黒写真を見ると、時代の流れを感じるとともに、どことなく無機質な印象を受ける人が多いかもしれません。 書籍『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』は、そうした白黒写真への印象が「戦争と私たちの距離を遠ざけ、自分ごととして考えるきっかけを奪っていないでしょうか?」(本書より)という「問い」から始まりました。AI(人工知能)と人とのコラボレーションによって白黒写真をカラー化するという取り組みは、東京大学に在学する庭田杏珠さんと、東京大学大学院情報学環教授の渡邉英徳さんが共同でおこなっている「記憶の解凍プロジェクト」です。 本書で渡邉さんは以下のように記します。 「カラー化によって、白黒の世界で『凍り付いて』いた過去の時が『流れ』はじめ、遠いむかしの戦争が、いまの日常と地続きになります。そして、たとえば当時の世相・文化・生活のようすなど、写し込まれたできごとにまつわる、ゆたかな対話が生みだされます」(本書より) その言葉のとおり、写真が彩色されることで、人々の肌に生気が生まれ、自然は四季の色合いを見せ、街は活気づき、まるで凍っていた世界が生き返ったかのように感じます。 たとえば、とある家族が親戚と一緒にスイカを食べている写真、理髪店の前で撮られた仲が良さそうな母と息子の写真(アニメ映画『この世界の片隅に』冒頭シーンのもとになったといいます)、川で大勢の子どもたちが水遊びをする写真など。身近な日常の風景ばかりで、この中に自分のおじいちゃんやおばあちゃんがいてもおかしくないという気持ちにさせられます。 それは、戦争の写真についても同じです。空襲で焼け野原となった街、特攻隊の発進を見送る家族、玉音放送をラジオで聴いて涙を流す人々など、カラーで見る戦争の様子は大きなリアリティをもって胸に迫ってくるものがあり、「これは本当に起きたことなのだ」とその重みを突き付けられる思いです。 AI技術によって「自動色付け」はできるものの、それはあくまでも「下色付け」。最終的には、戦争体験者との対話や資料などをもとに手作業で色を修正して仕上げるそうです。たとえば、本書でも大きなインパクトを持つ、広島市に原子爆弾が投下されている写真。AIはきのこ雲を白く着色したそうですが、『この世界の片隅に』などの映画監督・片渕須直さんからの指摘や資料などを参考に、オレンジ色に寄せて色補正を加えたといいます。 カラー化された写真からはさまざまな物語が感じられます。戦争を「遠い昔の話」として風化させないためにも、この本を通して一人でも多くの人に当時の暮らしに思いを馳せていただきたいです。