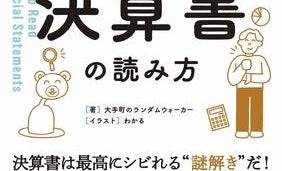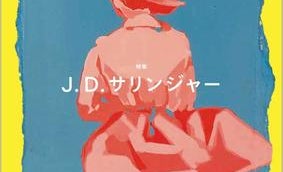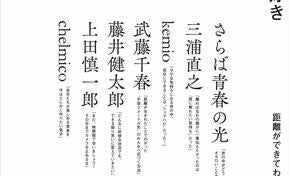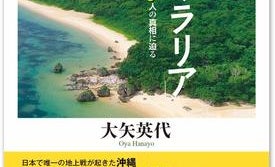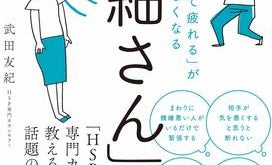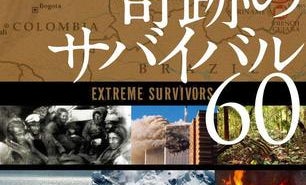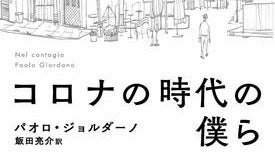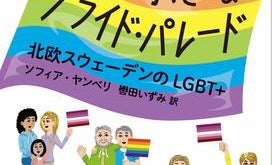
ソフィア・ヤンベリ&北丸雄二が語る、「LGBT+とBLM運動」から「マイノリティの中のマイノリティを意識する」考え方
2020年4月24日、ミツイパブリッシングより『ぼくが小さなプライド・パレード 北欧スウェーデンのLGBT+』(著:ソフィア・ヤンベリ/翻訳:轡田 いずみ)が上梓されました。本書は、スウェーデンのLGBT+当事者たちの本音を伝える書籍として注目されています。 本書の刊行を記念して先日開催されたのが、著者のソフィア・ヤンベリさんと、ジャーナリストの北丸雄二さんによるオンライントークイベントです。そこでどのような会話が繰り広げられたのか、その一部をここでご紹介します。 スウェーデンでは同性婚が合法となったり、トランスジェンダーの人の性別変更が法的に認められていたりと、LGBT+先進国といった印象があります。ソフィアさんはスウェーデンの学校教育について、自身の思い出とともに次のように語りました。 「学校でジェンダー平等に特化した授業はないけれど、たとえば歴史の授業で『なぜ女性の発明者が少ないのか』ということから、先生がこれまでの女性の社会的役割について話すことがありました。このようにジェンダーの平等や性的指向の話が授業中に出てくるので、自然とそうした考えが身につきます」 ソフィアさんは23歳のときに自分がバイセクシャルであることに気づきますが、こうした考えの土台があったことから、家族や友だちに隠すことなく話せたといいます。 また、現在大きな広がりを見せている「BLM(Black Lives Matter=黒人の命だって大切だ)運動」は、アメリカではLGBT+団体の連帯が表明されるなど、マイノリティに対する包括的な運動へと発展しています。こうした流れの中でキーワードとなってくるのが「インターセクショナリティ」です。 インターセクショナリティとは、「人種や性的指向など一人ひとりが持つ属性や、それによる差別の構造は多層的で交差している」という考え方のことです。これについてソフィアさんはこう話します。 「LGBT運動の中にもいろいろな人種の人がいるし、黒人の中にもLGBT+の人がいる。フェミニズムは昔から白人女性の問題に集中しているところがあったけれど、黒人の女性や他の人種の女性たちも、『私たちの権利や問題も重要だ』と話すようになりました。『マイノリティの中のマイノリティを意識する』という考え方が、まさにインターセクショナリティそのものなんです」 そして、北丸さんもこれに同意します。 「LGBT+の中でも、L(レズビアン)、G(ゲイ)、B(バイセクシャル)、T(トランスジェンダー)と、それぞれの中でいろんな分かれ方をしていて、さらにQ(クエスチョニング)もあればI(インターセックス)もある。僕たちはまずLGBT+という大きなところから考えて、今『その中でも一つひとつ違うんだな』ということに気づいた段階にいる。LGBT+は、一つひとつが連帯してインターセクトしていることを表すための言葉。いろんな人たちが重なって共有できる部分・共通した部分を軸にして何かを訴えていったときに大きな力になると思う」 本書には、スウェーデンにあるLGBT+のための老人ホーム「レンボーゲン」に住むゲイ男性・トーマスさんへのインタビューが収録されているほか、ゲイやレズビアンのカップル、LGBT+の子どもを持つ親、移民のLGBT+など、多様性あふれる人々が登場します。ソフィアさんと北丸さんのトーク内容に興味を持った方は、本書を手にとってみてはいかがでしょうか。