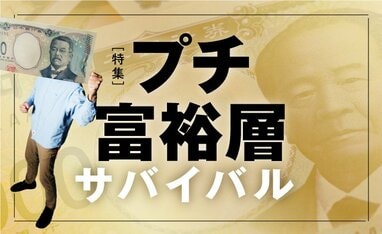一冊の本



10月号美術史家 門脇 むつみ Kadowaki Mutsumi十七世紀画壇のスーパースター
狩野探幽(かのうたんゆう)(1602~74)は、五代続く画家の名門に生をうけ、徳川家康の御用(ごよう)をつとめ、秀忠以降、家光、家綱の御用(お抱え)絵師となり、後水尾(ごみずのお)天皇をはじめとする宮廷の愛顧を得て、73歳で亡くなるまで精力的な活動を続けた。江戸城や御所の障壁画から画帖(がちょう)の小さな画面まで、瀟洒(しょうしゃ)な山水画、迫真の肖像画、華麗な歌仙絵、可憐な花鳥画など、どんな絵にも巧みであった。生前から圧倒的な名声を誇ったが、死後も大きな影響力をもち続け、狩野派が江戸時代を通じて幕府御用絵師の地位を守り日本の画壇を牽引する基礎をつくった画家として顕彰されてきた。








8月号茨城大学教授・マヤ考古学者 青山和夫 Aoyama Kazuo「真の世界史」から学ぶ
私たちが、中学・高校で学んだ世界史は、「真の世界史」では決してない。それは、西洋史が西ヨーロッパの列強とアメリカ合衆国、東洋史が中国を中心とする「偏った世界史」である。世界はいわゆる旧大陸の「四大文明」だけではなかった。メソアメリカとアンデスという、コロンブス以前のアメリカ大陸の二大文明を十分に語ることなくしては、世界史を正しく再構成できない。なぜならば古代アメリカの二大文明は、旧大陸と交流することなく、「四大文明」と同様に、もともと何もないところから独自に生まれた文明、つまり一次文明を独自に形成したからである。

特集special feature






5月号甲南大学教授 田中貴子 Tanaka Takako青い鳥を探して
ふた昔、いや、ひと昔前でも、オジサンと呼ばれる年代の男性が通勤電車で開く本は時代小説が多かった。それも、剣豪小説と呼ばれる男性作家のものばかり。しかし現在、時代小説はもう「男の聖域」を離れ、世代や性別を問わず広い読者層に親しまれるようになった。その功績者は、女性の時代小説作家だと言ってよいだろう。忠義と剣に生きる「おさむらい」に、お色気悪女か純情おぼこといったステレオタイプな女が絡む小説を喜ぶ読者ばかりではない(ドラマの「水戸黄門」に由美かおるの入浴シーンが1回はあるようなヤツですね)。女性時代作家の特色は、今まであまり描かれることのなかった職業や境遇の人々を細やかに語る点である。本書の著者もその一人だ。