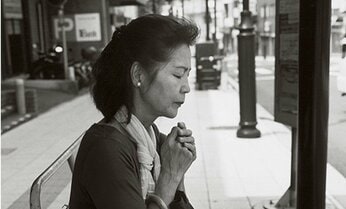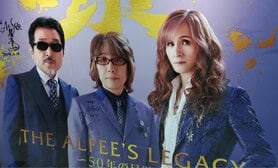早稲田、明治、芝浦工大…広まる「100分授業」の功と罪 一部学生からの“不満”と大学側の“新たな悩み”とは
これまで大学の授業期間といえば、半期で90分授業を15回行うのが主流だったが、最近は100分14回に変更する大学が増えてきた。2017年に明治大学や芝浦工業大学などが100分授業を導入して以降、上智大学、法政大学、立教大学、早稲田大学などが続いた。背景にあるのは、大学教育の質的転換に向けて13年に大学設置基準が改正され、多様な授業期間の設定が可能になったことだ。ただ、100分授業に対して「総授業時間が増えた」「昼休みの時間が短くなった」など、学生から不満の声が目立つという報道もある。早い時期に100分授業を導入した明治大学と芝浦工業大学に導入の理由や、学生らの反応を取材した。