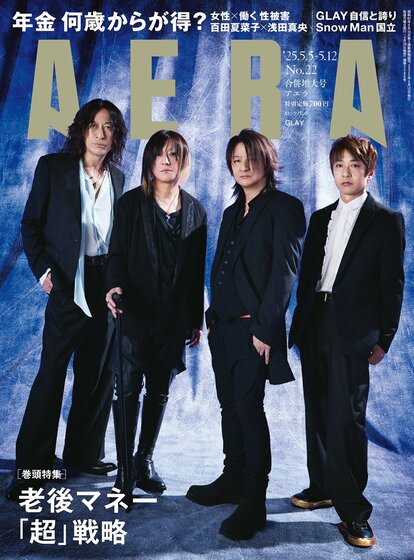たとえば、深川・富岡八幡宮には横綱力士碑や大関力士碑があるし、回向院には故人となった力士たちのための力塚も作られている。余談がだ、国技館が両国にあるのは、天明時代から長く勧進相撲を開催し続けてきた回向院が両国にあり、この流れを継いだからである。
このほかにも、芝大神宮(芝神明宮と称した)には、歌舞伎の題目にもなった「め組のけんか」(興行中の力士とめ組の争い)と書かれた狛犬、勧進相撲で発行された縦番付のほとんどを所有している蔵前神社などがある。
今の土俵の上には神社の屋根がついているのをご存じの方も多いだろう。あの形は神明造とよばれるもので、伊勢神宮のお社の形と同じ姿である。余談だが、屋根の上に横向きについている丸い棒のようなものは鰹木(かつおぎ)、屋根のはしにVの字のように伸びている棒を千木(ちぎ)という。この2つの形で、その神社に祭られている神さまが男神か女神かを表す慣習がある。当然であるが、両国国技館の屋根の形は男神を祭るものだ。加えて、四方から伸びている房はもちろん柱に見立てられているものだが、黒・赤・青(緑)・白色に分かれているのに気がつかれただろうか。これらの色は、東アジアに古来ある「四神相応」(四方の方角を守る神)のそれぞれの神が持つ色で、方角を表しているのだ(北=玄武、南=朱雀、東=青龍、西=白虎)。こうやってみていくと、相撲がどれほど神さまとともに歩んできたかがおわかりいただけると思う。
今は力士にモンゴル人が多くなったが、ふた昔前にはハワイ出身力士が多かった時代がある。そのため、ハワイ巡業なるものも多く行われた。ハワイには日系移民も多かったことから、とても喜ばれたようだが、もうひとつ私はおもしろいことに気がついた。横綱大鵬の千社札をハワイ・オアフ島の石鎚神社でみつけたのだ。外国へ行っても、お相撲さんはやっぱり神社へでかけるのだな、としみじみと思ったのだった。(文・写真:『東京のパワースポットを歩く』・鈴子)
あなたの知らない神社仏閣の世界特集トップへ