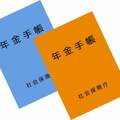それでも見放せなかったのは独居を気の毒に思う気持ちがどこかにあったから。
「火の不始末などからご近所に迷惑をかけられたら娘として困るな、とも。だから、年々ひどくなる母のもの忘れが、2017年にやっと受診にこぎつけた医療機関で即、アルツハイマー病と診断された時も、一人娘である私の介護負担が、この先どんどん重くなることだけが憂鬱でした」
看取りまでしてくれる施設を見つけた時は、心底ホッとしたそう。
「母の介護も看取りもできないという自分の気持ちに迷いはありませんでした。支配的で、思い通りにならないと攻撃的になる母の性格を、子ども時代は恐れ、大人になってからは嫌悪してきました。母の施設入居でようやく解放される、と」
施設でも生来の性格のまま案外楽しそうに暮らす母。
「認知症のおかげで母はもう死の恐怖や孤独と無縁。私や家族、周囲にしたことの責任も取らずにあの世にいくなんて、なんてずるい、卑怯だろうと思います」
老いた親の介護には、それまでの家族関係の質と歴史が凝縮される。
過干渉、精神的・身体的な暴力、教育虐待、親の依存症などによるきびしい母娘関係を生き延び、ようやく自分の人生を歩み始めた女性たちが、介護が必要になった“重すぎる母”と再会する時、どんな道を選ぶのだろう。それが、拙著『きらいな母を看取れますか? 関係がわるい母娘の最終章』(主婦の友社)に取り組んだきっかけだった。
まず、親からの虐待サバイバーが、老親の介護に複雑な感情を抱くのは男性も同様とはいえ、関係を母と娘に限定したのは、介護される・する側ともに女性が多い現実を重ねたからだ。
老いてなお、娘の人生に干渉し、介護は当然、将来は墓を守れ、などと言い募る母を持つアラフォー世代の女性を“墓守娘”と名付けたカウンセラー、信田さよ子さんの著書『母が重くてたまらない 墓守娘の嘆き』(春秋社)が刊行されたのは08年だった。
それから12年たった今、50代になった“墓守娘”にとって、70代から80代にさしかかった母の介護にどう向き合うかが、切実な問題になってきたのだ。