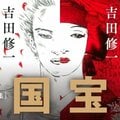声を上げやすい環境をつくるための取り組みもある。例えば、ヨウコさんの事業所では、毎週行うミーティングの際には、議事録に残さない“フリートークタイム”を設け、どんなことでも話してよい時間を作っている。相談のハードルを低くする試みだ。
もし利用者からのハラスメントに悩む職員がいたら、まずは本人がどれだけの不快感やストレスを感じているのかをしっかり聞く。ヨウコさんはマネジメントとして声を聞く立場にもあるが、そのときに「自分基準で判断しない」ことを心がけているという。
■介護サービスは信頼関係が肝
「大切なのは、ハラスメント的な言動を受けた人が、どう感じているか。そのときに、上司自身の価値観を押し付けてしまうと、結果的に職員を守れない。職員を守るためには、職員の心の声と考えを聞かなくてはなりません。本人がストレスを感じている場合には、担当や現場を変えるなどして対応するようにしています」(同)
利用者からのハラスメントに対する対策は、個々の事業所や個人の判断に委ねられている部分も大きい。今後、介護を必要とする人がますます増えることが予想される中、ハラスメントに胸を痛めて業界を去る人がいるのは深刻な問題だ。深刻化する問題に対し、利用者やその家族はどんなことに気をつける必要があるのか。
「介護サービスを受けるには、最低限のマナーを守る義務があることを、利用者側も職員側もしっかり認識しなければならない」と話すのは、前出の結城教授。結城教授が指摘するのは、「職員が福祉の視点で利用者と関わることが、声を上げづらい環境につながっている」という点だ。いわく、相手が“介護を必要としている人”となると、「どこまで問題にしていいのか」「弱い立場の人を相手に、声を上げてよいのか」と迷う職員も少なくないという。
「まずは、いくら介護を必要としている人といえど、最低限のマナーは必要で、配慮することも当然の義務。それが守れない人は介護を受ける資格がないことを、利用者も介護者も認識すべきです。介護は、いわば究極の対人サービスで、信頼関係が何より大切。その信頼関係は、相手への配慮やマナーなしには成り立ちません。特に公的な制度による介護サービスを利用する以上、今後は介護者に対して最低限のマナーが守れない利用者に対し、罰則を設けるなどの規定も必要になってくるかもしれません」(結城教授)