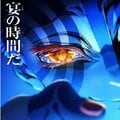■笑顔で「知らないふり」
小学生くらいの子どもなら、勉強を教えてもらうのも楽しい。
「学校や塾で学んだことを、子どもに教えてもらいましょう。親は『先生、ここはどうすればいいですか?』などと、生徒役に徹します。アウトプットすることで、子どもの理解も深まりますよ」
しかし、親子のコミュニケーションは、プレ思春期の兆しが見え始める小学校中学年くらいから難しくなるもの。それまでは、子どもの方から「聞いて、聞いて」と話をしてくれていたのに、親より友達が大切になり、家では一気に口数が減ってくる。
「とくに忙しいお父さんは、意識しないと、子どもとの会話がなくなってしまうでしょう。すると、子どもの興味や行動が見えなくなり、親子の距離もどんどん開いてしまいます」
そこで、坂本さんに子どもの話を聞く際に心がけたいコツも聞いた。
「笑顔で話を聞くことです。うんうん、とうなずくなどのリアクションもいいですね。さらに、『知らないふり』も効果的。当然知っていることでも、あえて『へえ、それはどういうこと?』と聞いてみるのです。このコツを『親子の会話が続かない』と悩んでいた保護者のお父さんに伝えたことがあります。しばらくして経過を聞いたら、『話をするときの子どもの表情が明るくなりました』と報告してくれました。話題も増えたそうです」
たとえ15分でも、あきらめてしまうのはもったいない。話を「聞く」ことを積み重ねれば、信頼関係を築くことができる。
「そのうちに、子どもから愚痴や悩みを聞けるようになれば、親子関係は最高だと思うんです」
一日の中で、1時間は難しくても、15分なら全力で向き合える。今日は子どもになにを聞こうか。(ライター・三宅智佳)
※AERA 2022年7月18-25日合併号