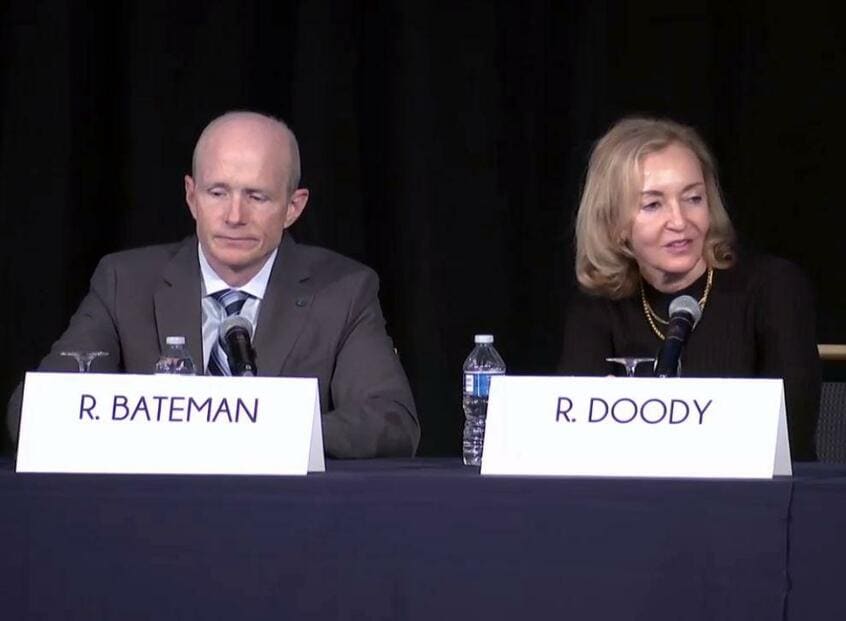
11月29日から12月2日まで米国サンフランシスコで行われたアルツハイマー病の治験の国際的な学会Clinical Trials on Alzheimer’s Disease(CTAD)に参加した。と言っても、現地に行ったわけではなく、ウェブからバーチャルに参加できるチケットを買って。
このウェブで参加できるチケットでも、1120ドル(約15万6800円)するから、決して安くない買い物なのだが、どうしても聞きたい発表があったのだ。
日本のメディアの多くの関心は、現地時間11月29日の夕方に行われたエーザイのレカネマブの最終治験「フェーズ3」の詳細なデータ発表にあっただろう。なにせ、初めて病気の進行を27パーセント遅らせるという治験結果が出たからだ。
私は、レカネマブの発表にも興味があったが、翌日のある「失敗した治験」の発表のほうこそ、見るべき発表だと考えていた。
アルツハイマー病の抗体薬の開発の抄史は、9月27日発売の10月7日号ですでに書いている。当時メディアの大半は、アミロイドβという脳内にたまるタンパク質を標的とした抗体薬の創薬に懐疑的だった。というのは、2000年から始まったアミロイドβを標的とする薬は、AN1792から始まり、バピネツマブ、ソラネツマブ、そして直近のアデュカヌマブまで認知機能の面での効果を証明できずにきたからだ。
そうなると、そもそもアミロイドβを標的とする「アミロイドカスケード仮説」自体が間違っている、という識者のコメントを載せるメディアも出てきた。
しかし、私は、こうしたメディアの報道は、ひとつひとつの治験の中身を見ずに語っている、と前回指摘した。たとえば、2010年代には、まだ脳内のアミロイドを測るアミロイドPETが普及しておらず、現在では、2割から3割のアルツハイマー病ではない認知症の患者が治験に入っていたことがわかっている。さらに初期の治験では、画像上脳に浮腫がみられる副作用(ARIA=アリア)の正体がよくわからず、薬の投与量を極端に減らしていた。






































