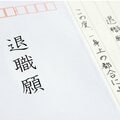「判決では削除したファイルについて、『退職した従業員が会社の業務に従事する過程で作成し、会社の管理する共有サーバー内に保存していたものであるから、特段の事情がない限り会社は保護される利益がある』とし、これを再度作成するために必要な人件費や外注費の相当額として約580万円を認定し賠償を命じました」
冒頭の女性についても、「業務中に作った書類をすべて破棄、もしくは改ざん」して辞めた場合、徳島地裁判決のケースと同じように損害賠償責任を負うリスクがある、というわけだ。
「退職時のトラブルとして、『引き継ぎを拒む』ケースはよくありますが、単に引き継ぎが不十分なだけでは違法とは言えないことが多いです。後任の業務を妨害するレベルにまで至っている、と判断された場合のみ損害賠償責任が生じます」(西川弁護士)
データの「破棄」や「改ざん」は訴訟で「意図的な妨害」と認定されることが多いため、賠償責任を問われる可能性が高いという。
「リベンジ退職」というワードは最近よく聞くようになったが、退職をめぐるトラブルは以前からあるのも事実。そんななか近年目立つのは、「転職サイトへの書き込み」だと西川弁護士は指摘する。
「採用難の時代に会社のイメージダウンは致命的なリスクになるため、転職サイトの口コミの内容に敏感になっている企業が増えています。実際ここ数年、企業からの相談も増えています」
書き込み内容が虚偽と立証できれば、裁判所への開示請求・決定を経て、投稿者を特定する情報の開示を求めることができる。悪質なケースは投稿者に損害賠償請求することもある。ここでポイントになるのは、書き込み内容が虚偽であることを客観的に立証できるかどうかだ。
例えば、「残業代が支給されない」「平均年収はもっと低いのが実態」といった書き込みは社内記録と照合すれば、容易に虚偽を立証できる。一方、仮に「会社の将来性に疑問を感じる」とか「上司が無能だ」といった書き込みの場合、一方的な主張だとしても「虚偽」と立証するのは難しくなる。
「会社にしてみればすべて『悪口』に映るかもしれませんが、虚偽だと証明できなければ転職サイトの公益目的に照らして違法とはいえないと判断され、削除の要求も通りません」(同)