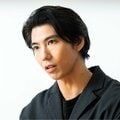血液検査に加えて、アレルゲンエキスを皮膚に付着させるなどして腫れの有無を調べる「皮膚テスト」や、小麦を摂取して症状の有無を確認する「食物経口負荷試験」が実施されることもある。
小麦アレルギーと診断された場合、対策は「小麦製品を食べたあとに症状を誘発するような行為をしない」が基本となる。特に注意したいのが運動で、アレルギー症状は小麦製品を食べて2~4時間後に運動すると起こりやすいという。
「歩いた程度で症状が出る人もいて、どの程度の運動で症状が出やすくなるかについては個人差があります。ただし、運動強度が高くなるほど、症状が出るリスクも高くなります」(福冨医師)
小麦製品の摂取のポイント
小麦製品の摂取についても気になるところだが、小麦アレルギーの人すべてが完全に除去する必要はないそうだ。
「もちろん、アナフィラキシーが出やすい重症の人や心臓病がある人は命に関わることもあるので、完全に除去する必要があります。そうでなければ、小麦製品を食べたいかどうかという患者さんの希望に合わせて対応します」(福冨医師)
心臓病の人が服用していることが多い、血液をサラサラにする薬(抗血栓薬)の一種である低用量アスピリンは、解熱鎮痛薬と同様にアレルギー症状を誘発しやすい。さらに心臓病がある人がアナフィラキシーを起こすと、命に関わるリスクが高くなる。
実は小麦はパンや麺類のほか、カレーやシチューのルゥ、天ぷらの衣、菓子・スナック類など、さまざまな食品に含まれている。
基本的には摂取した小麦の量が多いほど、症状が出やすい。
福冨医師によると誤って食べてしまうケースが多いのは、「小麦入りの米粉パンやパン粉を使ってあるハンバーグ、とんかつ」などだそう。しょうゆや味噌、穀物酢などの調味料や麦茶、ビールにも含まれていることがあるが、その程度の量では、基本的には症状は引き起こさないケースが多い。
現在のところ、アレルギーが起こる原因を取り除く以外治療法はないが、誤って食べてしまった場合のアナフィラキシーに備えて、アドレナリン自己注射薬「エピペン」を携行することが推奨されている。
子どもの小麦アレルギーは成長に伴って治ることが多いが、大人の場合はどうか。
「患者さんの経過を調査していますが、基本的にはよくなっていません。一度発症したら生涯付き合っていく病気と考えたほうがいいでしょう」(福冨医師)
成人の食物アレルギーは近年急増しているため、専門的な知識を持つ医師が限られているのが現状だ。
「アレルギー科を受診するのが基本ですが、どの病院に受診すればよいかわからないといった場合は『都道府県アレルギー疾患医療拠点病院』に相談するのがいいでしょう」(福冨医師)