そう考えると、本当の病気になる手前の段階には、より多くの人が「未病」状態で存在することになります。漢方では、精神疾患になってしまう前のメンタル不調、うつ症状が出ている状況を得意としているのです。
さらに治療のスタートは早ければ早いほど、治りやすいのです。私の診療所は、子どもの患者さんも多いのですが、漢方薬がとてもよく効きます。というのも、親御さんはメンタルの不調がある子どもに対して、抗うつ薬などを服用させることに抵抗がある傾向があります。最初から漢方薬を希望して当院を受診されるので、早めに治療ができ、漢方薬も効果を発揮しやすいのです。一方、大人の場合は、抗うつ薬を飲めばなんとかなると考えているのか、限界までがまんしてしまう傾向があります。そしてうつ病を発症し、抗うつ薬を服用したけれど、副作用で継続できないなど、こじらせてしまうことがあるのです。
日本のような保険制度がない米国は医療費が高額になるため、健康意識が高く、まさに未病の段階でケアするという考えが広まっています。一方、日本は病気になっても病院に行けばいいと医師任せにしがちです。本来は、自分のからだは自分で守るべきなのです。
健康維持にも漢方薬
未病には、現在のところ不調はないが、将来に備えて準備をするという意味合いもあります。例えば不調を自覚していなくても、舌診で舌に歯形がついていれば、「水毒」のサインです。この場合、水の巡りをよくすることで水毒の人に起こりがちな頭痛などを未然に防ぐことができます。
病気をきっかけに漢方薬を飲むようになって、その病気が治った後も健康維持、健康増進を目的に漢方薬を飲み続けている人は、少なくありません。30年以上飲み続けている人は珍しくありませんし、私の患者さんでは60年以上飲んでいた方もいます。
前述の『黄帝内経』に「上工(じょうこう)は未病を治し、已病(いびょう)を治さず(腕のいい医者は未病を治して、すでに病気になったものは治さない)」という言葉があるように、症状や病気となって表面化していない「未病」を見つけて治す医師こそ、名医としているのです。
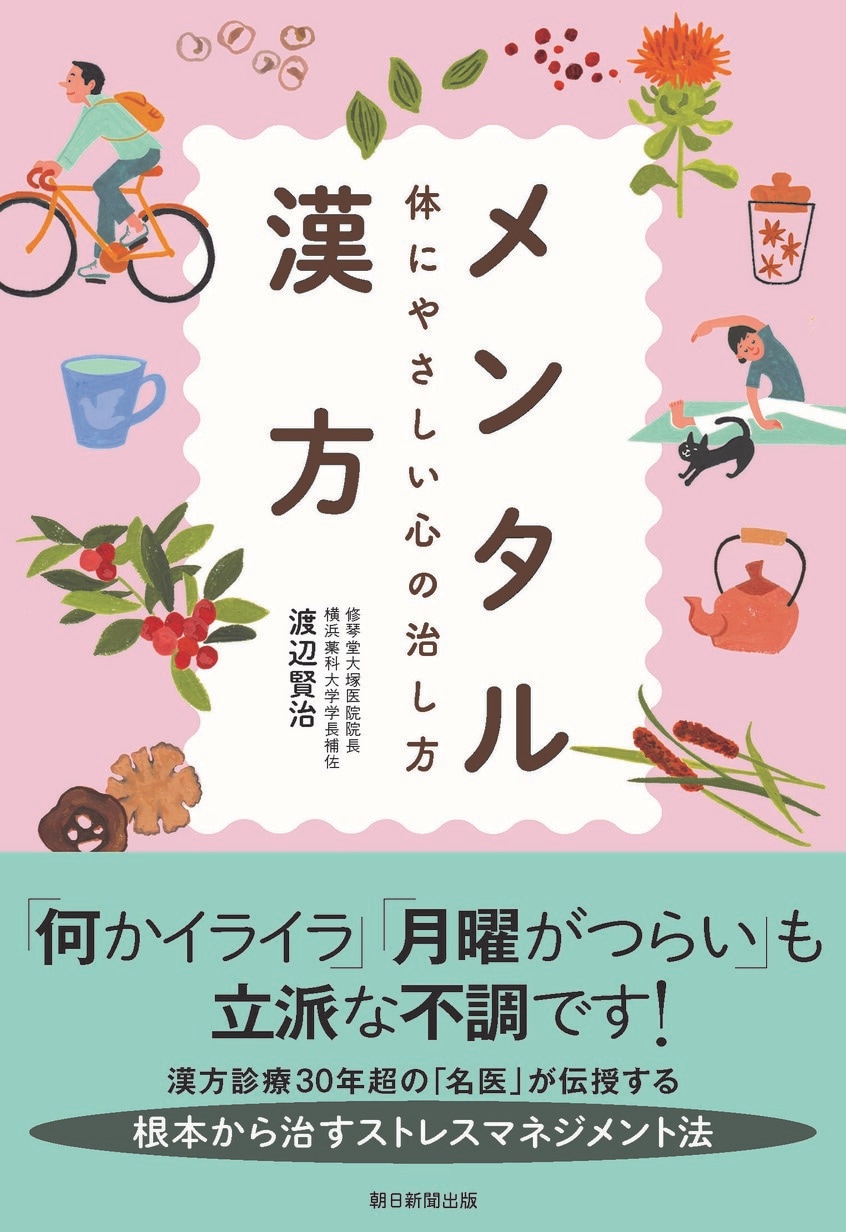
※『メンタル漢方 体にやさしい心の治し方』(朝日新聞出版)から一部抜粋
こちらの記事もおすすめ 漢方診療30年超の医師「メンタル不調の患者を診る機会が増えてきた」 心と体は一つという考え方








































