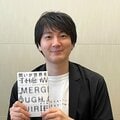今年1月、『東大理三の悪魔』(宝島社)が刊行された。
とても面白い。
東京大理科三類(3年次に医学部進学)と言えば日本最難関で、全国の選りすぐりの秀才が集まるところである。いったい、どんな人間が集まっているのだろう……そんな好奇心に十分応えてくれる内容だった。いや、それ以上かもしれない──この本をひもとく前は、宇宙の真理の一端が垣間見えるとは思いもよらなかったのだから。
タイトルに理三を冠した本書では、理三の学生が普段からしていそうな会話、議論、悩みなどを覗かせてくれる。登場人物はみな個性豊かで、魅力的である。主人公と仲良しである秀才の岡田、奇才の蔵野。彼らの考察は切れ味が鋭く、洗練されている。さすが理三の学生だと唸らせるものがある。そして主人公のタムラはつらい過去を持つ秀才で、同時に謙虚な心を持つ青年でもあった。
彼らの議論は常人では理解しがたいほどぶっ飛んでいる一方で、驚くほど地に足のついた議論でもある。物理学、生物学を極めた学生だからこそ既存の知識を柔軟に使いこなすことができるようだ。だがしかし、ここに文字通り次元の異なる天才が現れるのだ。彼の語る「生々しい」理論体系にタムラは「背筋がゾクゾク」するような感覚を覚える。
著者は東京大理三、医学部出身で医師の幸村百理男さん。現在は離島で医院を運営している。幸村さんに、天才とは何か、理三とはどんなところかなどを伺うとともに、受験生へのメッセージも寄せてもらった。
――『東大理三の悪魔』を著すに至ったきっかけを教えてください。
理三はよく「天才たちの集団」と紹介されることがあります。しかし実際に私が目にしたクラスメートは勉強のできる秀才たちで、良くいえばスマート、悪くいえばオーソドックスな考え方をする人たちでした。受験エリートとは、大人たちが期待する答えを返すプロなのですから、当然のことだったかもしれません。
私は中学時代から天才への憧憬(しょうけい)を持つようになり、その姿をよく空想していました。受験生のトップが集まる理三だったら憧れていた天才に会えるかもしれない──そんな期待は打ち砕かれる形になりました。もちろん、単に私のアンテナが鈍かった可能性は否定しきれません。