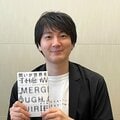さらに③はこの直線的な思考が条件に応じて分岐するわけですから、直線的思考が並列に進む形になります。これは不完全ながらも二次元的思考と考えることができるでしょう。
これらアルゴリズムの要素は単純ですが、それが無数に集まることによって巨大な情報処理が生まれるわけです。ところが、アルゴリズムが苦手とするのが物事の認識です。たとえばある人間の顔を見せてそれが誰かを認識させるのは、アルゴリズムにとって難問となります。その写真の点の一つひとつを一次元的、あるいは一次元の並列(不完全な二次元)で処理しようとするからです。
ところが我々の脳や最近はやりのAIは、これらの処理を難なくこなすことができます。それは上記の3大要素にみられるような一次元的思考ではなく、二次元、三次元と分布する演算処理装置を使用しているからです。
たとえば皮膚の触覚は、典型的な三次元の解析装置と言えます。多くの場合、「理解した」ときのスッキリする感覚は、一次元的思考が二次元、三次元に拡張された時に生じます。「論理は一次元、理解は…」の言葉はその感覚を端的に表したものと言えるでしょう。
タイトルの「悪魔」に込められた意味
――物語は主人公のタムラを軸にして進んでいきます。この小説は「実話を元にしたフィクション」と紹介されていますが、タムラは幸村さんをモデルにしたのですか?
正確には「私とそっくりな人生を送っている別人」です。ちなみに岡田や蔵野も実在の友達がモデルになっています。このへんの話は宝島社から出版された『東大理三の悪魔』のあとがきに詳しく書かれていますので、是非そちらをご覧いただければと思います。
――『東大理三の悪魔』の悪魔にはどんな意味がこめられていますか。
「マクスウエルの悪魔」という有名な言葉があります。ここに登場する「悪魔」の解釈は諸説あるのですが、私はこれを熱力学という整然とした理論体系の中に、「意識」という異質の存在を組み込んだ考えだと解釈しています。つまり「悪魔」とは、理論という枠組みの中の「特異点」のような存在です。
同じように理三という秀才集団の中に紛れ込んだ桁外れの天才、すなわち「特異点」というニュアンスで『東大理三の悪魔』という題名が思い浮かびました。
――幸村さんにとって理三はどんな場所でしたか?