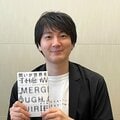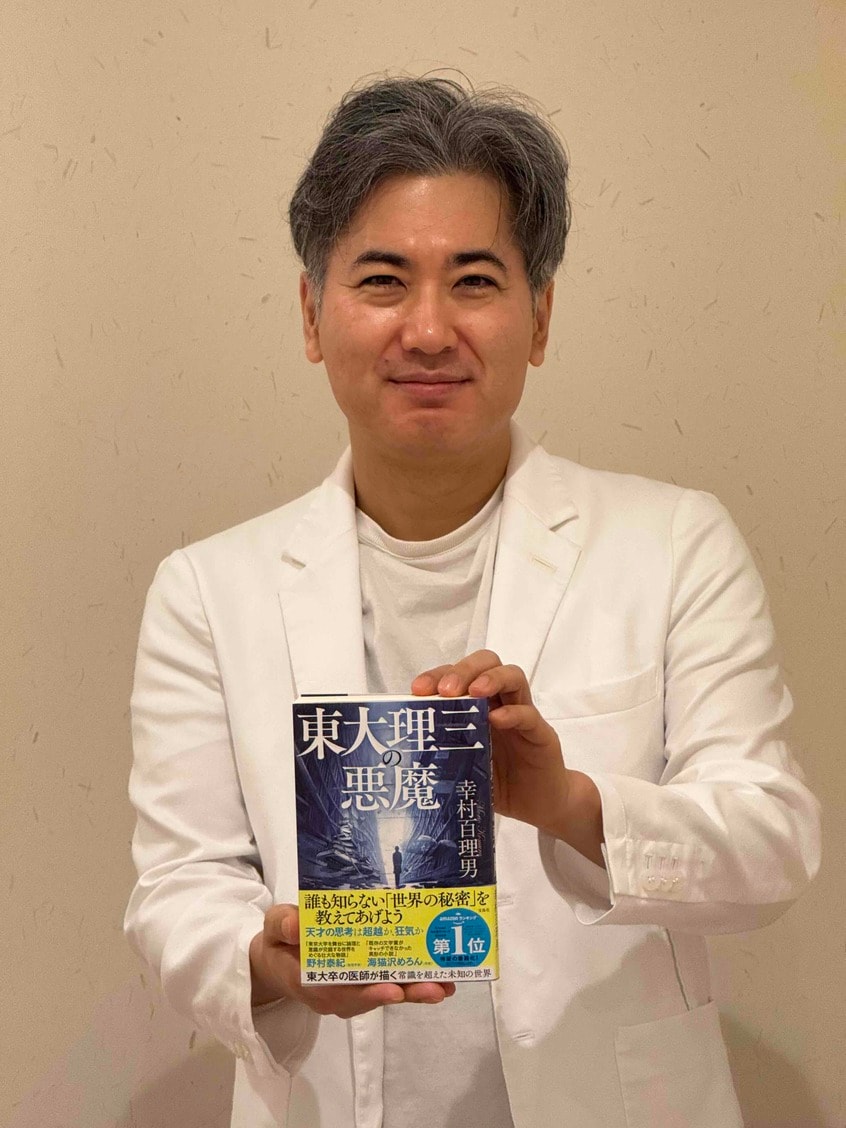
この小説に出てくる岡田は「典型的な理三」の人間です。ソツがなく、自己管理に長けていて、勉強もできる。彼を理三の標準的人物として読み進めてもらうと面白いと思います。そして理三の中ではアウトローとも言える存在、奇才の蔵野も登場します。彼もまた秀才の一人ですが、社会人経験者で世間擦れしている分、物事への洞察に長けています。
この物語は私の記憶をなぞるように進んでいきます。ただ一人、特異点となる存在がいて、それが天才である間宮惣一です。
主人公のタムラノボルは間宮の語る「生々しい理論」に夢中になります。一方で間宮が抱える苦悩は、19歳の少年にとってあまりにも深刻なものでした。その困難を乗り越えようとする二人の絆にも注目していただきたいです。
論理は一次元的、理解は二次元的
――本書では主人公のタムラノボルが「論理は一次元的、理解は二次元的、実感は三次元的である」という言葉を羅針盤にして成績が急伸する回想シーンがあります。これについて詳しく話してもらえますか?
例えばプログラミングを例に考えてみたいと思います。アルゴリズムには3大要素と呼ばれる概念があって、それぞれ、①繰り返し処理(同じ処理の繰り返し)、②順次処理(順番に似たような処理を繰り返す)、③分岐処理(場合分けをして処理)と呼ばれます。このようなプログラミングは単純計算に強いのですが、我々がごく日常的に行っている認識の作業は苦手です。その理由について考えてみましょう。
まずは①について考えてみましょう。例えばひたすら1を足していく計算(1+1+1+……)が典型例です。これはいわば同じ場所にずっととどまるような思考──0次元的思考と言えます。
そして②は、たとえば1+1+5+7+……というように、異なる数の和に例えることができます。これは①の単純計算に近いけど、処理内容(足すもの)は変わっているわけです。これは①の0次元的思考に対して、まっすぐな線の上を進んでいくような思考、つまり一次元的思考と考えることもできます。