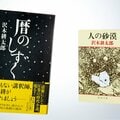前著『アルツハイマー征服』の出だしは青森のりんご農家から始まる。りんご農家の主婦の陽子は40歳になるころから、りんご栽培の作業がうまくできなくなる。収穫のときに、りんごの実ではなく葉をもいで籠いっぱいに積んで帰ってきたとき、一族のものたちはささやきあう。
「陽子にもまきがきた」
「まき」とはその地方特有の言葉で、「遺伝性の」という意味だ。
私が遺伝性のアルツハイマー病のことを知ったのは、この本の取材を始めて2年ほどたった2004年の話。青森にその大きな家系があるということで、何度も通うことになる。
デール・シェンクという今日のレカネマブにつらなる創薬のアイデアを最初にだした科学者と会って取材をスタートしたときには、すぐにでもアルツハイマー病の治療薬ができると思っていた。
が、そう簡単なものではないということがわかるのは、シェンクの理論にのっとった最初の薬AN1792が脳炎の発症により治験が中止になり、その次の薬バピネツマブもフェーズ2で結果がだせなかった2007年ころの話だ。
青森の家系については、弘前大学の医学部のチームが1980年代からずっとおいかけていたが、そのうちの医師の一人田﨑博一に話を聞いたときのことである。
晩秋の青森は夕方になるともう暗く、田﨑の部屋も暗かった。その暗い部屋で田﨑が、「治療法がないので、遺伝子検査をしてもやりようがない」と訥々と語ったのを聞いて、治療法のめどがつくまでは私もこの本を書くことはできないと悟ったのだった。
家族会もなく、家系の人々はひっそりと暮らしている。思春期になると親がアルツハイマー病になり、その世話が始まる。やがて自分たちにもそうした運命が2分の1の確率でやってくることを経験的にわかっている。
その発症が40代ということもあり、新薬の治験にも入れないのだった。治験のプロトコルには「60歳以上に限る」といった年齢の制限があるからだった。製薬会社にとっては遺伝性のアルツハイマー病は別の病気であり、統計上のノイズになる、そう判断しているということもわかった。