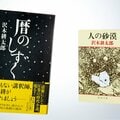10余年後、医師は言った「今は希望があります」
もういちどこの本に取り組んでみようと思ったのは、2017年暮れのことだ。個人的な事情もあったが、10年がすぎて、大きく事態が動いていることを知ったことが大きかった。
その中でも、私の気持ちを後押ししたのは、DIANという遺伝性アルツハイマー病の人々の国際的な研究が始まったのを知ったことだった。
遺伝性のアルツハイマー病はアルツハイマー病全体の1パーセントにみたない。が、その突然変異が受け継がれれば100パーセント、若年で発症する。これらの人々の観察研究をすることは、一般のアルツハイマー病にも応用できるはずだ。そうしたことから、アメリカのワシントン大学のランディ・ベートマン博士らが始めた研究で、国際的なネットワークをつくることで、被験者の数を増やすということがアイデアの根本にあった。
このDIAN研究に日本も参加をし、弘前大学はその拠点のひとつになっていた。
DIAN研究やレカネマブの話を書くことで、「今は希望があります」という後の田﨑の言葉をそのままひいたタイトルのエピローグをつけて『アルツハイマー征服』の文庫版を出したのが、昨年8月ということになる。
「進行抑制」から「進行停止」へ そして「予防」へ
そのDIAN研究が今、遺伝性アルツハイマー病の家系の人々を対象に、おおきな意味を持つ治験に取り組み始めている。
この治験には、発症前の人でも参加できるのだ。
レカネマブとの併剤で、タウの抗体薬を投与するとどうなるかを見る。
アルツハイマー病の病理はふたつあり、脳内にアミロイドβというたんぱく質がたまって凝集していくこと、そしていまひとつは神経細胞内にタウという物質が固まった神経原線維変化という糸くずのようなものがたまっていくことだ。
このふたつの変化が発症の20年以上前から始まり、認知症の症状が出てくるということになる。
治験では、エーザイが開発中の「E2814」という抗タウ抗体薬を投与する。被験者には全員抗アミロイドβ抗体薬レカネマブが投与され、そのうえで「E2814」を投与される人と偽薬を投与される人にわけられ、4年後の変化を比較する。
日本では新潟大学と東京大学が治験の拠点となるが、新潟大学で日本のDIAN研究をひっぱってきた同大教授の池内健とは、単行本の取材のときからのつきあいだ。