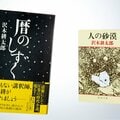池内も医者として、長年遺伝性アルツハイマー病の家系の人々とつきあってきた。
弘前大学にいた田﨑と同じように、アルツハイマー病の治療法がない、ということに苦悩していた。
その意味で進行を27パーセント抑制するレカネマブの承認は大きな朗報だった。そして今度の治験は、これを病気の「進行抑制」から「進行停止」、そして「予防」にするための大きな一歩なのだった。
3月14日に日本におけるこの治験の記者会見が新潟大学で行われたが、池内の表情は晴々としていた。
DIAN研究は日本では始まって10年以上がたつが、そこに参加する人たちは、自分たちが間に合わなくとも、次の世代の解決法につながれば、という「いちずな思いから参加してきた」と述べ、それが今回初めて治験という形で「自分たちの世代で何かができるかもしれない、という形に変わった」。
「そういう選択肢を提示できた」
日本では、これまで遺伝性アルツハイマー病の家系の人が発症前に遺伝子検査をすることはほとんどなかった。が、今回の治験に参加をするためには、遺伝子検査をうけて突然変異を持っているかどうかを調べ、本人もその結果を知らなければならない。
全世界16ケ国、39施設、168名が参加をして行われる今回の治験に日本からの参加者は4名。4人の年齢は30代から50代で、未発症者が2名いる。
このうちの一人は、治験に参加するか否か(つまり自分の遺伝子の状態を知るか否か)、相当苦慮したという。が、記者会見で、池内は、被験者も「この治験で予防の方法を探りたいとしている」とその結果を前向きにとらえていると語った。
また、遺伝子検査の結果、陰性がわかり治験に参加しないことになった人もいた。
そしてこの結果を本人に伝えるのは、池内や主治医ではない。
それを伝える専門の医者やカウンセラーがいるのだが、誰が伝えるか、いかに伝えるかについての物語が私の次のテーマだということになる。
なお、今後の遺伝性アルツハイマー病の治験の問い合わせは、新潟大学脳研究所生命科学リソース研究センター(dian-j@bri.niigata-u.ac.jp)まで。
※AERA 2024年4月22日号