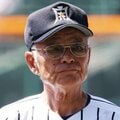元日に起きた能登半島地震でも、ペットとともに被災した人が多数にのぼった。
【チェックリスト】災害時に飼い主は何をすべきか。備えておきたい防災用品
発災時には「同行避難」ができたとしても、避難所で様々な問題に直面して自宅に戻ったり、車中で過ごしたりする人も後を絶たない。熊本地震(2016年)の際に問題になった、一緒に避難所で生活する「同伴避難」の困難さは今回もあらわになった。19年の台風19号の際には犬2匹、ウサギ2匹を飼っていた男性が、自宅でペットとともに多摩川氾濫の犠牲になったこともあった。ペットの飼い主として、これから起きる大規模災害にどう備えればいいのか、いま一度考えてみたい。
* * *
「ペットと同行避難をすることは、動物愛護の観点のみならず、飼い主である被災者の心のケアの観点からも重要である」
環境省が18年3月にまとめた「人とペットの災害対策ガイドライン」に出てくる一節だ。
東日本大震災(11年)で一部のペットが自宅に取り残され、つながれたまま亡くなったり、放浪して行方がわからなくなったりする悲劇に見舞われた。こうした事態を受けて環境省は、大規模災害の際には「飼い主とペットが同行避難することが合理的である」とする基本的な考え方に立ち、各種ガイドラインをまとめてきた。

「同行避難」に備える
いまや同行避難は、ペットの飼い主を中心に、広く浸透している。だが、いざという時、実際に同行避難するためには、やはり日頃の準備が欠かせない。
まず、自宅の近くでペットとの同行避難が可能な避難所はどこなのか、地元自治体の防災計画や動物愛護管理推進計画などを確認しておく必要がある。
そのうえで、実際にペットを連れて、その避難所まで行ってみよう。犬ならリードにつないで一緒に歩いて行けるかもしれないが、猫やウサギ、鳥など、キャリーケースに入れなければ運べない動物では、そこまで持ち運べるかどうか、体力が試される。特に複数のペットを飼育していれば、連れて行くことが物理的に可能かどうかは、深刻な問題になる可能性がある。
また、留守がちな家庭では、近所の人にペットの存在を周知しておくのも一つの手だ。発災時にどこまで頼れるかは未知数だが、家屋が倒壊したり、火災が発生したりした場合、屋内にペットがいることを近所の人たちが知っているかどうかは、少なからずその後の対応に影響するはずだ。「逃げ出すのを見た」などの目撃証言を得られるだけでも、飼い主として何をすべきか変わってくる。