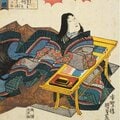四年後、赦免された親鸞は、建保二年(一二一四)、妻恵信尼や息子たちとともに常陸へ移住する。同国を選んだ理由は不明だが、法然の弟子だった下野の御家人宇都宮頼綱、またはその一族の招きによるともいわれる。以後、二十年間、親鸞は常陸にとどまり笠間(茨城県笠間市)の稲田草庵(現在の西念寺)を拠点として布教活動にはげんだ。
当時、東国の武士や百姓が信仰していたのは、加持祈祷によって豊作や健康などを祈る呪術であった。そのような人々に対して、親鸞は阿弥陀仏への信仰が人々を救う唯一の道であると説いた。特に、悪人こそ阿弥陀仏の本願によって救われるという悪人正機説は、殺生を家業としてきた武士の心を強くつかんだことだろう。
関東での布教活動を通じて念仏の意義、他力本願の確信を得た親鸞は、文暦元年(一二三四)頃に帰京した後、『教行信証』を著す。国内外の経典や解説書を踏まえて、自身の念仏・往生の思想を体系化したもので、浄土真宗の根本聖典となった。また親鸞の死後、異端の信徒が増えたことから、河和田(水戸市)の唯円は正統の教義を伝えるため『歎異抄』を著し、その思想をわかりやすく広めた。
その後、末娘覚信尼の孫の覚如は、親鸞の大谷廟堂を寺院化して本願寺を創建。八世蓮如の時、大規模な教団の組織化が図られ、戦国大名をも脅かす政治勢力に成長していく。
こちらの記事もおすすめ ライバル謀殺に「策」をめぐらせた中臣鎌足 日本史上最強の「藤原氏」だったのは一日だけ