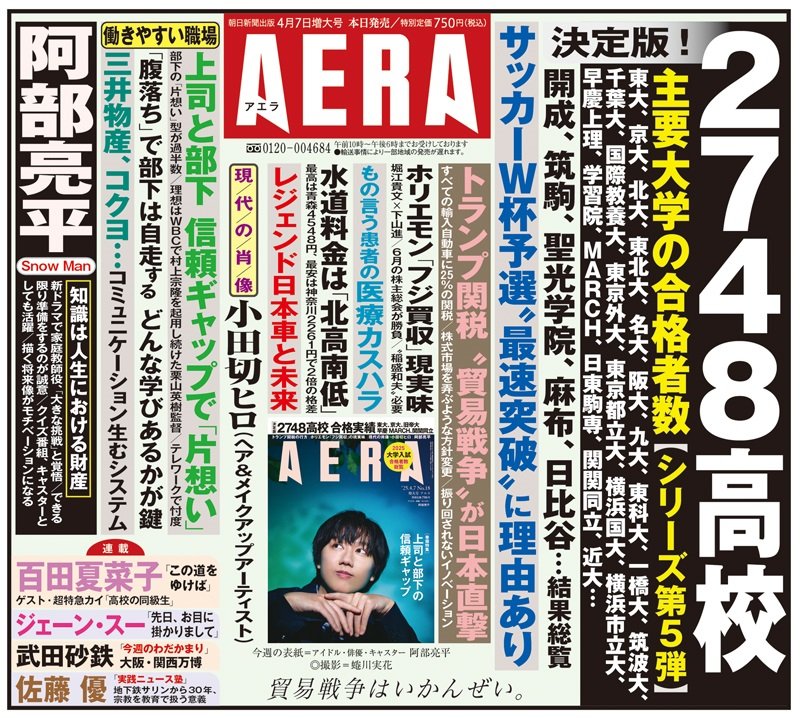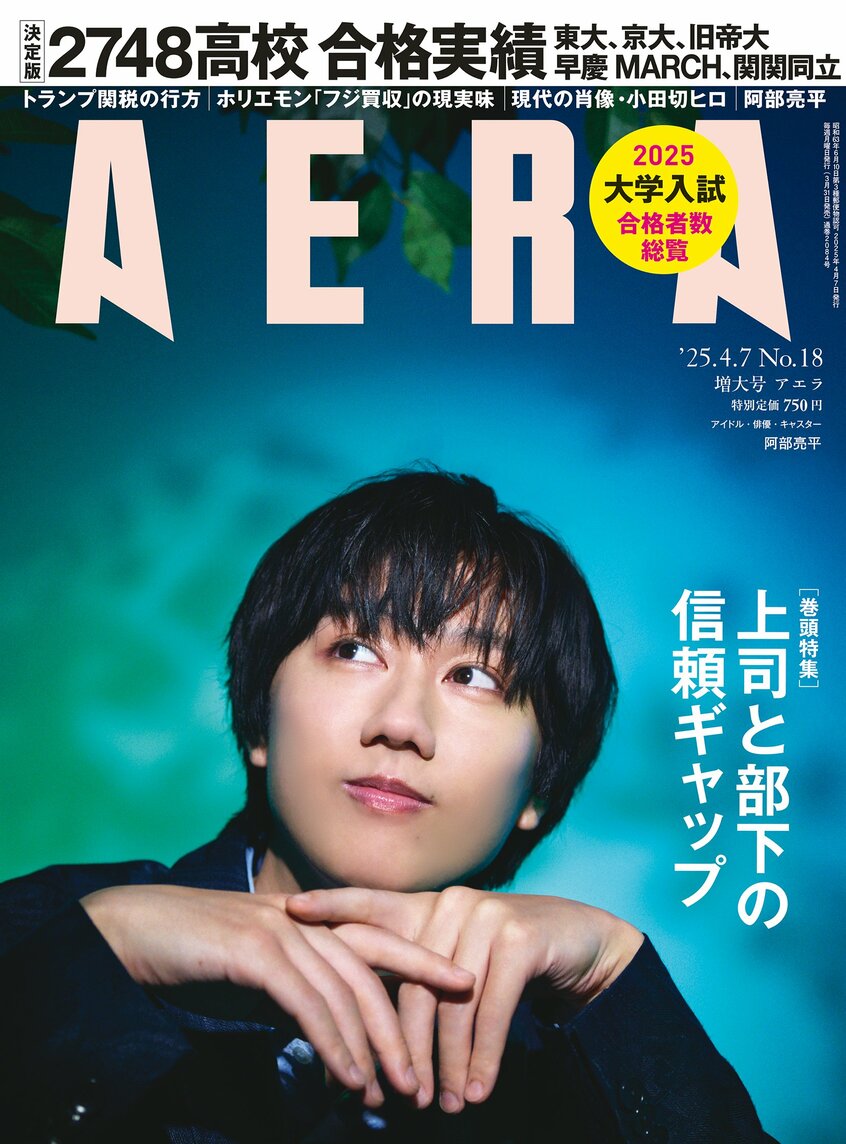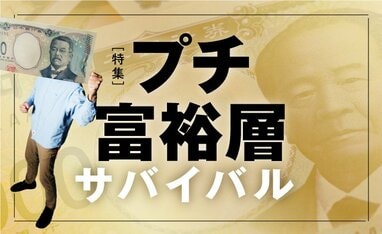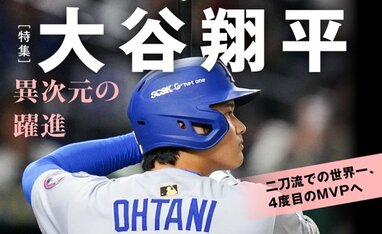免疫を勉強したくなったんです。そうしたら、3年生の実習のときマウスを殺さないといけなくなって。私は殺すのがつらくて、心が痛んでしまった。それで、微生物にしようと思った。微生物に興味があったわけじゃないんですけど、一番心が痛まないから。
4年生で微生物の研究室に入り、放線菌の研究をして、自分で考えてやっていくのは楽しいなと思って、修士までは行こうかと思った。ところがその先生は定年退職されるので、ほかを探さないといけなかった。試験管の中にいる微生物より、自然環境にいる微生物を研究しているところがいいと思って探したら東大(農学生命科学研究科)にあったので、そこに入りました。
でも、あんまり楽しくなかった。実験がうまくいかなかったというわけではなかったけれど、さっき話したように、論文を書くために研究しているようなところがあって。ただ、ほかの世界を知らないから、社会はこういうものなのかなあと思っていた。
――よく我慢しましたね。
子どものころに読んだエジソンとかキュリー夫人とかの伝記では、どんどん科学にのめり込んで、ご飯を食べるのも忘れる、みたいなことが書いてあったのに、大学院ではそんな面白いことには一度も立ち会えなかった。ただ、それはまだ修業が足りないからなのかもしれないと思い、科学の面白さが見えるときまではがんばって続けてみようかと思ったんですよ。
博士号を取ってから、岩手県釜石市にあった海洋バイオテクノロジー研究所というところの任期付き研究員になりました。海の研究を始めたのはここからです。南太平洋のパラオとかいろんなところに行ってカイメンなんかを採取して、そこから微生物を培養して、すごい楽しかったんですが、あるとき東大時代の教授や先輩から電話がかかってきて「研究室で大きな予算が取れたから、戻ってきてくれないか」というんです。迷ったけれど、何回も電話があり、釜石は寒いし、私は雪の上を歩くのが得意じゃなくてしょっちゅう転ぶし、父の転勤で両親が東京に引っ越していたこともあって、元の研究室に戻った。ところが3年目ぐらいで限界を迎えてしまい、研究ができなくなったわけです。
――そのころに結婚されたんですよね。どういう方と?