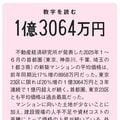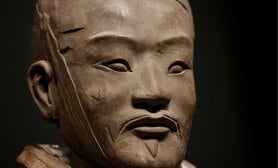■ただ口先で唱えるだけ
高橋:ユートピアは達成できないからユートピアなんです。達成できたら、ただの現実になってしまう。では、たどり着かないようにするためには、どうしたらいいのか。
ブレイディ:動き続ける、変わり続けるしかないんですよね。
高橋:そういうことだと思います。それともう一つ、浄土真宗では南無阿弥陀仏と念仏を唱えるだけで浄土に行けると言っています。親鸞はそれを徹底させた。ただ口先で唱えるだけでいいのだと。「そんなの仏教じゃない」と猛批判されても「いや、それでいい」と動じない。極端なことを言えば、その言葉を唱えれば、腹の中ではアッカンベーしていてもいい。
でも、その考え方って、宗教家というより文学者じゃないかって思うんです。文学者は口先だけだから(笑)。ぼくが親鸞に惹(ひ)かれるいちばんの理由は、親鸞は言葉を信じたことです。ある意味では、言葉だけを。それはすごいことだと思います。
ブレイディ:新約聖書にも「はじめに言葉ありき」とあります。やはり言葉なんですよね。だから文学を突き詰めていくと、宗教に興味を持たざるを得ないのかな。
■福岡のライブハウス
高橋:ところで、最近、ライターの鹿子裕文さんの『ブードゥーラウンジ』というノンフィクションを読みました。ほんとにおもしろかったです。それは、福岡に実在するブードゥーラウンジというライブハウスに集まってくる人々の話なんですが、彼らの歌は極度に個人的で、半径1メートルぐらいの狭い世界の中を歌っている。
ブレイディ:福岡のロックは「照和」(チューリップや海援隊が出てきた有名喫茶店)のフォークがルーツだったりするから、個人的な4畳半を歌いがちな文化があると思いますよ。
高橋:おもしろいなと思ったのは、たとえば、ボーカルとギター担当だから「ボギー」と呼ぶとか、ニックネームで呼び合っていてお互いの本名は知らなかったりすることとか。完全に外とは別世界なんですね。それから、ロックというと田舎から上京して成り上がっていくという出世物語はけっこう有名だけれど、この本に出てくる人たちはいまいる場所(福岡)から出ていかない。
ブレイディ:福岡にいるとそういうところはありますね。それで思い出したのは、私も同郷(福岡)の(女性解放運動家)伊藤野枝(1895~1923)ですね。彼女は自分の生まれた村の風習を嫌いながらも、そこにアナキスト的なコミュニズムの可能性を見ていました。山梨で育った(大正時代のアナキスト)金子文子(1903~26)もそうです。いつものメンツが集まって集合体ができあがっていくのは、田舎だからできるというところもあると思います。
高橋:ほんとうにそうだと思いますよ。伊藤野枝や金子文子が男性の社会主義者と違うのは、男性の社会主義者は都会人として割り切れる人が多い。男性は都会が好きなんだよね。そもそも都市の共同体は、個人個人はバラバラ。男性が唱える社会主義共同体なんてかけ声だけで、どこかうそ臭い。では求めるべき共同体はどこにあるのか。それは、自分が子どもの頃に過ごした田舎の共同体の緩やかな自己犠牲的な結びつきだったりするんですよ。若い頃はそれがうっとうしかったけど、いったん都会の生活を経験してみると、田舎のいい点が見えてくる。気がつかなかったものを再利用するというか、そこに人びとの知恵があったことに、女性革命家は気づくんですよ。彼女たちは底辺の生き方をよく知っているからですね。
(構成/編集部・三島恵美子)
※この対談は、朝日カルチャーセンター横浜教室で行われた講座を採録したものです。
※AERA 2023年3月27日号より抜粋