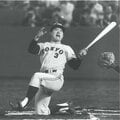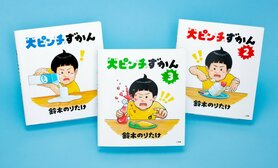阪神の背番号「44」といえば、真っ先に“伝説の助っ人”ランディ・バースの名が挙がる。
【ランキング】2022年セ・リーグ個人年俸上位20傑はこちら
バース退団から30年以上も経つ今でも「44番はバース」のイメージが強いのは、バースのあとにも先にも、背番号「44」を背負って長く活躍した選手がほとんどいないことを示している。歴代で虎の44番を背負った男たちを振り返ってみよう。
2リーグ制以降、1950年から68年にかけては、阪神の44番は8人中5人までが投手だった。野手組では、“ダンプ”の愛称で知られる捕手の辻恭彦も、若手時代の63年から67年まで44番をつけている。
筆者が初めて意識した阪神の背番号「44」は、藤田訓弘という捕手だった。
阪神がシーズン最終戦で優勝を逃し、巨人がV9を達成した73年、当時中学1年の筆者は、後楽園球場の左翼席で伝統の一戦を見る機会があった。
試合前の打撃練習で、一人の阪神の選手が柵越えを連発していた。スタンドのファンも「誰だろう?」と興味を抱くなか、目を凝らすようにして背番号を確認すると、「44」が見えた。第3の捕手だった藤田は、正捕手で4番を打つ田淵幸一の陰に隠れ、試合で見る機会がほとんどなかったとあって、「控えにこんな選手がいたのか」と目を見張らされたことを覚えている。
71年に出場16試合出場ながら2本塁打を記録した藤田だが、“和製大砲”として開花することなく、通算2本塁打のまま73年限りでユニホームを脱いだ。
その後、虎の44番は、ジョージ・アルトマン(75年)、ハル・ブリーデン(76~78年)、リロイ・スタントン(79年)、ダグ・オルト(81年)と、80年の中山孝一(投手)を除いて、一発長打タイプの助っ人たちの“指定番号”になり、俊足巧打タイプのグレッグ・ジョンストン(82年)を経て、バースに受け継がれた。85年に打率.350、54本塁打、134打点の三冠王を獲得し、日本一に貢献。翌86年にも打率.389、47本塁打、109打点で2年連続三冠王に輝いたバースの“神”と呼ばれる活躍ぶりについては、改めて紹介するまでもないだろう。