
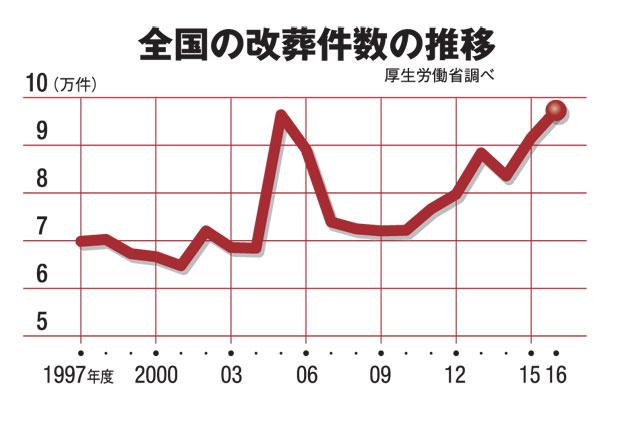
墓の在り方が揺れている。単身世帯の増加や人口減少の流れの中、家族の絆の象徴が「重荷」となる現実も浮かぶ。ライフスタイルの変化に合わせた新たな弔いの姿とは――。
* * *
石蓋が外された墓の内部に、白磁の骨壺が二つ、顔をのぞかせていた。黄泉の暗闇から一転、光に満ちたセミしぐれの現世へ。時の流れが逆行したような錯覚に包まれる。
酷暑の7月中旬。刺すような日差しが照りつける中、都立小平霊園(東京都小平市)で「最後の墓参り」が営まれた。
参列したのは、足が不自由な父親(79)と、その父に寄り添う長女(48)。霊園の一角に設営されたテントに腰を落ち着けた父娘は、ピンと張り詰めた雰囲気を解きほぐすように、こんな会話を交わした。
長女「久しぶりだね」
父親「3年ぶりかな」
墓の周囲を縁取る大谷石が少し欠けている。それを見て、長女が言う。
「いつだったか、お墓参りに来たとき、うちの娘が転びそうになって手をかけた拍子に崩れたんですよ」
家族の思い出が詰まった墓は翌日取り壊され、更地になる。
父娘は「床上げ」された墓前で焼香し、手を合わせた。「チーン」。父親が鐘を鳴らすと、別れのあいさつのように一陣の風が顔を洗った。
それが合図のように、遺族から「改葬」を委託された墓のサポート業者「石誠メモリアルサポート」(東京都府中市)の松本高明代表(60)が、「これからご遺骨を取り出します」と宣言。松本代表は身をよじらせながら、首元まで墓の中に入り、大小二つの骨壺を取り出した。
ひと回り小さな骨壺を指して父親が娘に言う。
「小さいほうが、おばあちゃんだよ」
ほろ苦い墓参りは約30分間で終わった。父親に胸中を問うと、こんな言葉が返ってきた。
「ほんとはね、断腸の思いなんです。娘も嫁いで、跡継ぎがいないもんですから……」
以前は春分の日と秋分の日の年2回、欠かさず墓参りをしていた。高齢に加え、体が不自由になり、車の運転ができなくなると、心の拠り所だった慣例も断念せざるを得なくなった。





































