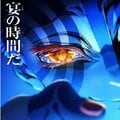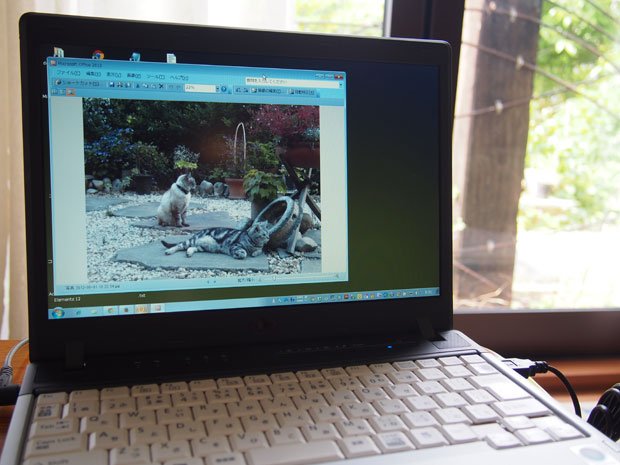
オンラインの学習ツールが、近年充実してきている。年齢や国境も超える、学びの魅力とは。
近年、世界中で急速に広がっているMOOC(ムーク)の概念。Massive Open Online Coursesの略で、世界のトップ大学の授業をオンラインで受けられる。世界中の誰もが高等教育を受けられる環境をつくり出した。世界的には、Coursera(コーセラ)やカーンアカデミーなどが有名で、2千万人が利用しているといわれる。
日本版ムークの最大手が、gacco(ガッコ)だ。「日本中世の自由と平等」「よくわかる! iPS細胞」など、大学や専門学校が提供する授業は教養から趣味まで幅広く、ひとつの講座を1カ月ほどかけてじっくり学ぶ。動画を各自のペースで見たあと、小テストやレポートの提出を経て、修了証が発行される。受講者同士でレポートの採点なども行うため、受講期間が設定されていて、いつでも受けられるわけではない。対面授業がある講座を除き、基本的には無料。「ボケ防止のため」という80代から、志望校の大学の講義を受けてみる高校生まで、受講者もさまざまだ。
「ムークは知のオープン化を生んだだけでなく、ヒューマンキャピタルの分野にも影響を与えつつあります」
ガッコを共同運営するNTTドコモライフサポートビジネス推進部の安川幸男さんは、そう説明する。
例えば米国では、コーセラの修了証をソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のLinkedIn(リンクトイン)に貼ることができる仕組みになっている。コーセラの受講は無料だが、修了証の取得にはコースにより数十ドルかかる。コーセラにとっては収益源のひとつであり、転職者にとっては「学び」の履歴をキャリアアップに有利につなげる手段となる。
「すでに米国では人材流動が激しいので、ムークの修了資格がキャリアパスになっている事例もある。単なる学習ツールではなく、自己実現ツールとしても活用されつつある」(安川さん)
※AERA 2015年6月29日号より抜粋