
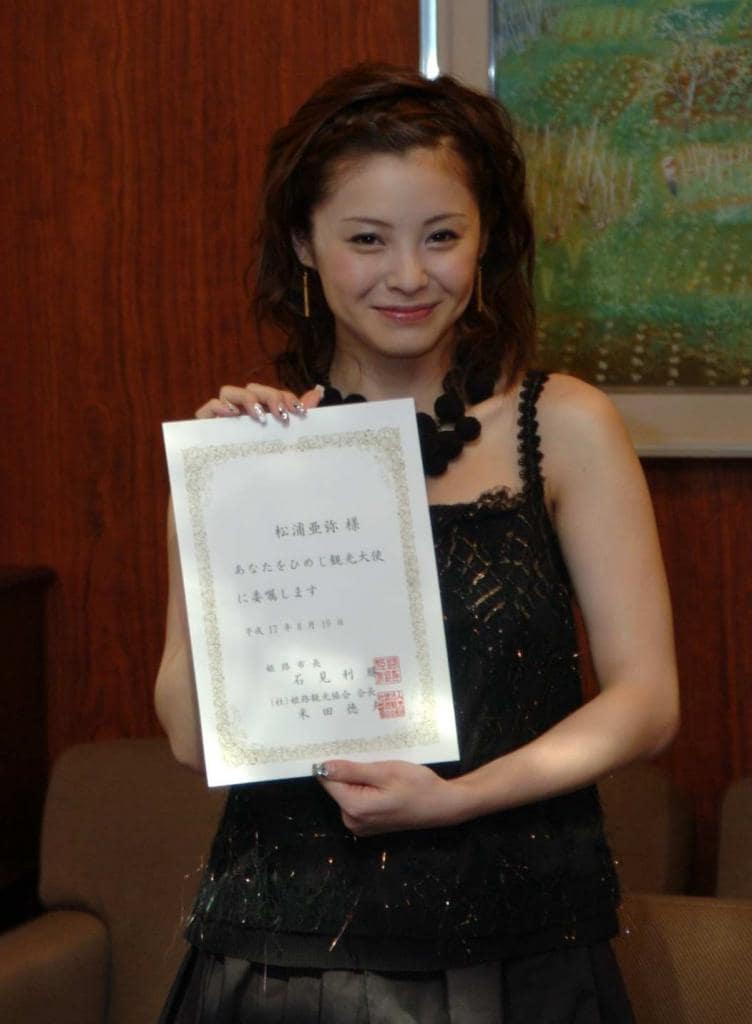

平成はアイドルの時代だった。男性ではジャニーズ勢、女性ではハロプロやAKB・坂道系が熱狂を生み、アニメの世界でも『ラブライブ!』のμ’sが異例の成功を収めた。ただ、それらはもっぱら「グループアイドル」の人気だったりする。昭和に時代の象徴とまで呼ばれた山口百恵や松田聖子クラスの「ひとりで歌うアイドル」は、ついに現れなかった。
もっとも、男性の場合は市場を独占するジャニーズがソロでの売り方を極力避けてきたことも大きいのだが…。女性の場合はそうではない。「ひとりで歌うアイドル」への挑戦は幾度となく繰り返されてきた。その歴史を、ここで振り返ってみようというわけだ。
まず、平成元年、宮沢りえがデビューした。美少女ブームとヒットCMなどの追い風を受け、小室哲哉プロデュースのデビュー作『ドリームラッシュ』は『ザ・ベストテン』の最終回にランクイン。しかし、3年4ヶ月後、のちの横綱貴乃花との婚約を解消した際、彼女はメディアからこんなことを言われてしまう。
「代表作がなかったりえにとって、この会見が代表作になるだろう」
彼女の歌は「代表作」としては見なされていなかったのだ。ではなぜ、そんなことになったのか。歌手デビューの前年、取材をしたとき、歌のレッスンを受けているというので話を向けてみると、こんな答が返ってきた。
「自分で歌いたい歌がわからない」
どうやら、CMやドラマ・映画ほどにはモチベーションが高くなかったようだ。これが『紅白』でバスタブに横たわりながら歌うなどの珍パフォーマンスにつながったのかもしれない。
ただ、当時は彼女に限らず、アイドルを目指そうとする、女の子たちの熱そのものが冷めつつあった。歌番組が減ったことに加え、自己主張もできるアーティストっぽい存在のほうがかっこいいという価値観が浸透してきていたからだ。
そんななか「最後のアイドル」と呼ばれたのが、高橋由美子である。こちらも、平成2年にデビュー。主演ドラマ『南くんの恋人』の主題歌『友達でいいから』はそこそこ売れた。





































