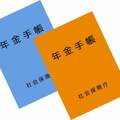男性が介護をする場合、その対象は平均寿命が長い女性、つまり母になることが圧倒的に多い。50代以上の全国の男性へのウェブアンケートでも、介護が必要な親を持つ人のうち、実に74%が「母」と答えた。
男性介護者として特に不利や苦労だと感じる点を質問したところ、
「親といえども相手は女性。男としてはシモの世話がしづらい」
「女性の生理的な面に関与できないし、したくない」
「母親なのでおむつや入浴介助を嫌がる」
といった異性間のギャップに由来する悩みが約60人から寄せられた。排せつ介助は、食事や入浴の介助と合わせて「3大介護」と呼ばれるが、そのケアは最も大変だという人もいる。人前では隠すべきとされてきたものに直接触れる行為は心理的な負担が大きく、介護する家族の中には義務感と抵抗感の間で引き裂かれて苦しむケースもある。
東京都町田市の契約社員、竹内昇さん(61)は3年前、長野県への里帰り中、認知症の母の介護を担う父が脳出血で倒れ、初の排せつ介助に直面した。母は尿意は伝えられたが、だれかが服を下ろしてポータブルトイレに座らせ、排せつ後に拭き取らねばならなかった。人間の尊厳にかかわる部分だけに、妻には頼みたくなかった。
「『おれがやる』と言ってはみたものの、初めて母のズボンを下ろすときは、かなり勇気が必要でした」
知的で美しく、幼いころから自慢の母だった。厳格だけれど、最後は自分を受け入れ、見守ってくれた優しい母。妻に「マザコン」と皮肉られても、返す言葉がないほど慕っていた。
「外見上の老いは受け入れていたつもりだったが、シワだらけで白髪の交じった性器を目にしたとき、自分の心にある母親像とのあまりの落差に涙が溢れました」(竹内さん)
父は一命を取り留めたが本人にも介護が必要になり、もはや母の世話はできなくなった。結局、両親を同じ特別養護老人ホームに入居させたが、今も面会するたびに罪悪感に苦しむ。
「本来なら自分がやらなければならないのに、他人任せにしてしまっているんです。卑怯な気がしてならない」(竹内さん)
こうした揺れる息子の心の叫びに、読者は何を感じるだろうか。実は、男性は女性よりむしろ介護に対する責任感が強く、抱え込みがちだと言われる。それを裏付けるデータの一つが、衛生用品大手ユニ・チャームが2013年に実施した介護する人が対象の意識調査だ。
「自分の力でなんとかなるなら精一杯やりたいか」との問いに、「そう思う」「ややそう思う」と答えたのは男性が70.8%。女性の54.2%を大きく上回った。また、「公共のサービスやヘルパーを利用するより、できるだけ自分でお世話をしてあげたいか」についても、男性の44.3%は「そう思う」「ややそう思う」と回答し、女性の34.7%をはるかにしのいだ。
孤立無援のまま、黙って母の老いに寄り添う中高年男性は少なくないはずだが、悩みあえぐ姿は見えにくい。その悩みを浮き彫りにするのが、排せつ介助だ。本誌アンケートの自由回答では「女子トイレには入れないので男子用に連れていくしかない」と大変さをつづった人がいた。トイレに行けても一人では無理という場合、異性の介助者が一緒に入れるトイレは限られる。
トイレ事情に詳しいNPO法人「日本トイレ研究所」(東京)の加藤篤代表が言う。
「車椅子マークのついた『多目的トイレ』なら男女の別なく一緒に入れるんですが、まだまだ数は少ないですね」
加藤さんによると、多目的トイレは一定規模以上の公共施設や駅、商業施設などに設置されているが、その質にはバラツキがある。新設の場合、多くは十分な広さが確保され動線もスムーズなのに対し、限られた空間に後から造られた場合、段差があったり、そこにたどりつくまで遠くて大変だったりするという。また、成人のおむつ替えができるベッドがあるケースは極めて少ない。
「多目的トイレは人工肛門を使う人や赤ちゃん連れなども利用します。高齢化で利用者は増える上、1回にかかる時間はどの人も長い。今後さらに需給がひっ迫する可能性があります」(加藤さん)
※ 週刊朝日 2014年10月3日号より抜粋