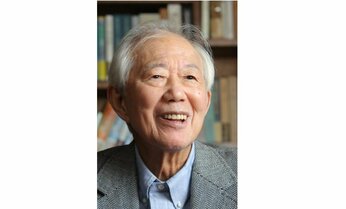「朝日新聞出版の本」に関する記事一覧


小学4年で英検準1級に合格した「ギフテッド」少年の生きづらさ 「正直、学校は好きじゃない」と適応に苦しみ
ギフテッドという言葉を聞いたことがあるだろうか。「飛び級で進学」「教科書は一度読めばほとんど理解」など、天才少年少女というイメージをもつ人も多いだろう。しかし本人は、「授業が全く面白くない」「同級生と話が合わない」「学校に行くのが辛い」といった負の側面を感じていることも少なくない。表からは見えづらい「心のうち」はいかなるものなのか。今回は、IQ154、小学4年生で英検準1級に合格したという小林都央さん(11)のケースを紹介する。<阿部朋美・伊藤和行著『ギフテッドの光と影 知能が高すぎて生きづらい人たち』(朝日新聞出版)より一部を抜粋・再編集>

「シン富裕層」が今でも“自宅投資”を成功させている理由 13年間で2億5000万円値上がりしたケースも
都心の駅近に1億円のマンションを購入すると10年でその価値が2倍に。そこで新たにローンを組んで2億円のマンションを買ったところ、3年後には3億5000万円に! そんな夢のような不動産投資を実現させている富裕層が日本にもいる。バブル時代の“土地転がし”とは違う才覚を持つ彼らは「シン富裕層」と呼ばれ、不景気でも着実に資産を増やしている。2万人以上の「シン富裕層」と関わってきたコンサルタントの大森健史さんが、その実態を解説する。(朝日新書『日本のシン富裕層-なぜ彼らは一代で巨万の富を築けたのか』から一部抜粋・再編集)





秀吉の悲願・豊臣家の存続が託された最後の城「京都新城」はなぜ幻となったのか 晩年の恐怖政治の象徴だった悲運
1597年、豊臣秀吉は生涯最後の城郭となる「京都新城」の築城を命じた。だが、その前後から秀吉は恐ろしい恐怖政治に突き進んでいた。政権を揺るがした「秀次切腹事件」にとどまらず、秀次家族全員の処刑、秀次重臣衆の切腹、聚楽第の破壊と、秀吉の命令は冷酷を極めた。政権崩壊のカウントダウンが始まるなかでの「京都新城」の築城は、豊臣家の存続という秀吉の悲願も託されていた。かつて幻の城郭といわれた「京都新城」について、城郭考古学者で奈良大学教授・名古屋市立大学特任教授の千田嘉博氏が読み解く。(朝日新書『歴史を読み解く城歩き』から一部抜粋)