
ビジネス

これからの企業に欠かせない「DX人材」が注目する業界別3つの最前線トレンド
著者の鶴岡友也さん。株式会社STANDARD 代表取締役CTO。1996年生まれ。明治大学在籍中から、AI エンジニアのフリーランスとして複数の開発案件に携わる。東大人工知能開発学生団体HAIT Labの運営を通じながら、株式会社STANDARD を共同創業。各産業のDX 推進支援やDX リテラシー講座の作成、グループ会社の設立などに従事。(撮影/写真部・張溢文) 著者の石井大智さん、鶴岡さんが経営する株式会社STANDARD。2017年の創業ながら、ソフトバンク・NTTデータ・パナソニック・リコー・みずほフィナンシャルグループなど、大手企業を中心に500社近くにDX人材育成、コンサルティング、プロダクト開発を提供している。(撮影/写真部・張溢文) 「いわゆるレガシーシステムはDX(デジタル・トランスフォーメーション)の足かせでしかありません。トラブル続きの銀行が典型ですが、早急に負債化している旧来のITシステムなどを整理して、より有効なデジタル技術を活用し続けなければいけない。どの企業にとっても明暗を分ける大きな課題であり、それを担うDX人材には、最新の成功事例の収集など、常にDXリテラシーの更新が求められます」
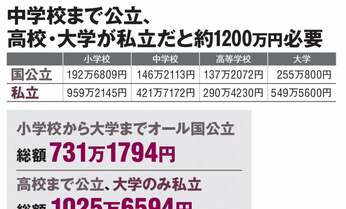


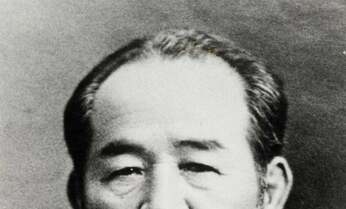

特集special feature



エンジニアの次は「DX人材」!価値高騰で採用マーケットに異変が
著者の石井大智さん。株式会社STANDARD代表取締役CEO。早稲田大学在学時より、製造業の効率化のための統計解析を学ぶ。東大生のメンバーとともに東大人工知能開発学生団体HAIT Labを設立し、学生AIエンジニア600人の集まるプラットフォームに育てる。AIエンジニアとして医療用AIの開発業務を複数社で経験し、現職(撮影/朝日新聞出版 写真部・張溢文) 著者の石井さん、鶴岡友也さん(右)が経営する株式会社STANDARD。2017年の創業ながら、ソフトバンク・NTTデータ・パナソニック・リコー・みずほフィナンシャルグループなど、大手企業を中心に500社近くにDX人材育成、コンサルティング、プロダクト開発を提供している(撮影/朝日新聞出版 写真部・張溢文) 「デジタル技術を活用して、顧客に価値を提供できるDX(デジタル・トランスフォーメーション)人材。そのニーズが採用マーケットで高騰しています。それは同時に、オールドタイプの企業に組織・文化の変更を迫る起爆剤にもなっています」


































