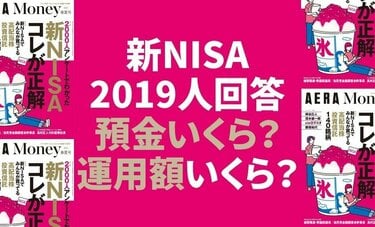【関節痛の予防】「肝(かん)」「腎(じん)」のケアで足腰を元気に
関節痛と深く関わっているのは五臓の「肝」と「腎」です。肝は「血(けつ)」を蓄え、血液循環によって「筋(きん:腱や筋膜など)」に栄養を送ることで、関節の働きをサポートしています。また、「精(せい:生命エネルギーの源)」を蓄える腎は身体の老化と関わっていて、骨や腰の状態とも密接に関係しています。
そのため、肝と腎の働きを守ることは、関節の老化を予防し、足腰を健やかに保つことにつながるのです。
特に、腎の機能は加齢によって自然と衰えていくので気をつけて。不調を感じていなくても、中年以降の年代(50代くらい)になったら積極的にケアをするよう心がけましょう。
また、「肝腎同源」といって二つの臓器は互いに影響しあって働いているため、肝と腎をバランスよく整えることも大切です。
<ワンポイント>
元気な足腰のカギとなる「精」と「血」は、食事の栄養から生み出されます。年齢を重ねると食が細くなりがちですが、「脾胃(ひい:胃腸)」を元気に保ってしっかり栄養をとることも心がけましょう。
<肝・腎が弱くなっているサイン>
足腰がだるく力が入らない、歩きにくい、関節がスムーズに動かない、関節の変形、慢性化した痛みやしびれ(膝痛、腰痛、下肢のしびれ、足のつりなど)、夜間頻尿、めまい、耳鳴り、目の疲れ、物忘れ、脱毛、白髪、舌の色が淡い
<食の養生>
身体を温め、腎を養う食材で老化予防を。
黒豆、松の実、くるみ、ごま、大豆製品、山芋、にら、豚足、鶏ガラ(鶏ガラスープなど)、手羽、牛テール(牛テールスープなど)、豚豆(豚の腎臓)、杜仲茶など
【関節痛の対策・その1】「お血(おけつ:血行不良)」を改善する
中医学には「不通則痛」という原則があります。これは、体内の気血の流れが悪くなると、痛みが起こりやすくなるという考え方。冬は寒さや湿気の影響で気血の流れが滞り、「お血(血行不良)」を招きやすくなります。そのため、関節痛を発症しやすく、痛みの症状も強く現れるのです。
また、「お血」の状態が長引くと、痛みが慢性化することも多いので気をつけて。しびれや軽い痛みを感じる程度でも、お血があれば積極的に改善することが大切です。
養生の基本は、身体を温めて血行の良い状態を保つこと。毎日の入浴、冷えない服装、温かい食事や飲み物などを心がけ、“身体の中から冷え予防”を習慣にしましょう。
<気になる症状>
しびれ、膝や腰の強い痛み、いつも同じところが痛む、冷えると痛みが悪化する、夜間の痛みが強い、関節の動きが悪い、関節痛が長期化している、顔色の黒ずみ、舌の色が暗い
<食の養生>
温性・辛味の食材で、身体を温め血行を促しましょう。
紅花、サフラン、よもぎ、シナモン、らっきょう、たまねぎ、ウコン、少量の酒など
 AERA dot.編集部
AERA dot.編集部