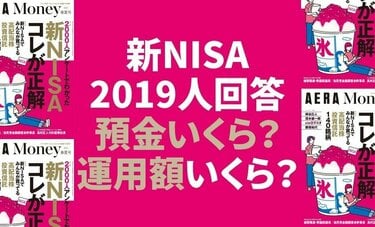■飲み薬または筋肉注射薬でしっかり治療する
治療の第一選択について、重村医師はこう話す。
「アモキシシリンというペニシリン系抗生物質の飲み薬になります。28日間連続、朝昼晩に服用する治療です。ヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応といって治療開始の初日に発熱することがありますが、薬の副作用ではなく、自然に軽快します。服薬の1週目以降に起こる皮膚の赤い発疹は、いわゆる薬疹(薬の服用により起こるもの)なので、気づいたら服薬を中止して担当医に相談する必要があります」
飲み薬のほか、2022年1月に発売された、持続性ペニシリン製剤(商品名:ステルイズ)という筋肉注射薬もある。感染から1年以内の早期梅毒なら1度の筋肉注射で治療が終了するのがメリットだが、新しい治療法のため実施していない病院もある。
治療後、症状がなくなって、血液検査で梅毒抗体の数値が治療前に比べて一定程度低下すれば治癒となる。当然ながら治癒までは性交渉は控える。
「症状の有無だけでなく、何度か受診して検査を受け、血清抗体価を確認しなければいけません。面倒かもしれませんが、治癒の状態にもっていかないと周囲にうつしてしまう可能性があります。これが、なかなか梅毒が減らない理由の一つだと思います」
■早期の受診・治療が重要。できれば専門医へ
性交渉時の感染リスクを減らす対策には、避妊具の使用が挙げられる。
「日本性感染症学会の啓発活動としては、専門外の医師に対して研究会などに出向いて周知していく予定です。個人的には学会の役職のほかに、大学病院の医師や大学教員でもありますので、20代の学生たちに啓発していきたいと考えています」
梅毒の診断の決め手になるのは、梅毒抗体の血液検査である。「心配な症状のある場合は随時検査を受けてほしい。症状がない場合の検査のタイミングは難しいが、感染が心配な時期から3カ月後の検査が重要です」と重村医師は話す。
 小久保よしの
小久保よしの