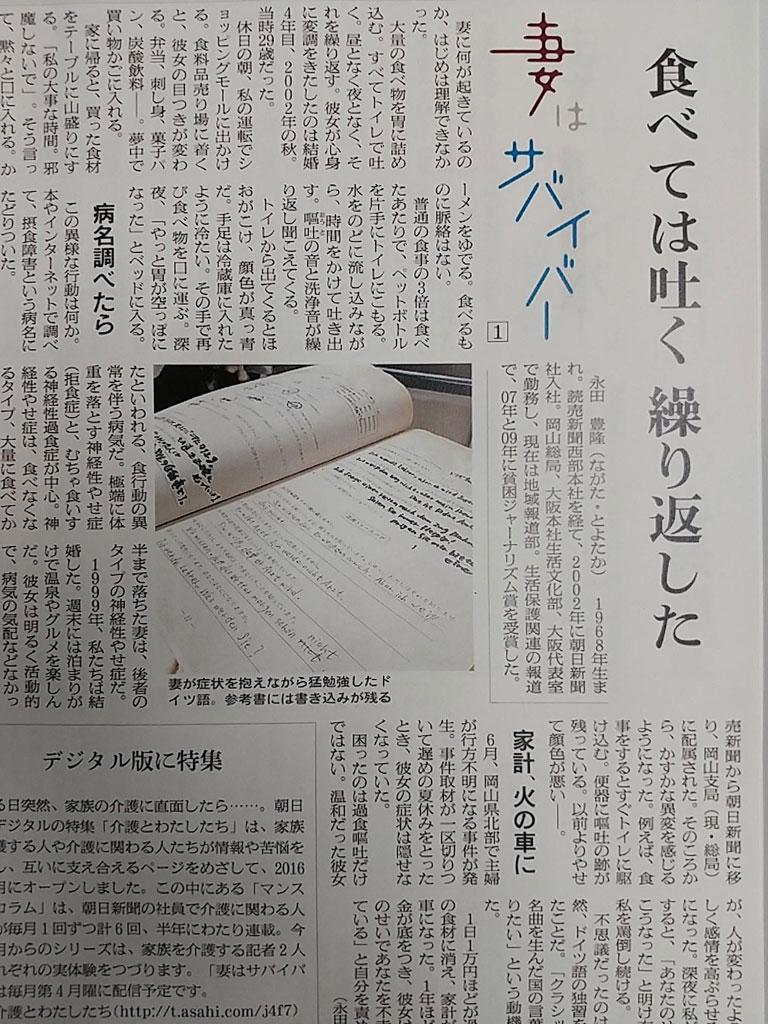
精神疾患を抱えた妻(49)の介護と仕事、その両立に悩み続けた20年近くにわたる日々──。朝日新聞デジタルで大きな反響を呼んだ連載に加筆した『妻はサバイバー』(小社刊)が4月に刊行された。著者で朝日新聞記者の永田豊隆氏(53)に、ともに本を作った編集者がインタビューした。
【人を愛するとはどういうことか──連載をまとめた本はこちら】
* * *
──本の発売から1カ月近く経ち、多くの感想が寄せられています。
反響の大きさにとても驚いています。「あまりの壮絶さに驚いた」というご感想をたくさんいただきましたが、私にとっては意外な感じがします。というのは書いたことは日常なんですね。やはり妻のような疾患のことはあまり知られていない。同じような障害を抱えている皆さんは、ひっそりと人知れず生きている。それが大きいんだろうなと思います。その壁が大きいからこそ「壮絶だ」という驚きにつながるように感じます。
──当事者の手記がほとんどない中で貴重な記録になっている、という評もいただいています。身近な方の反応をお聞かせいただけますか?
今回の出版を世界で一番喜んでいるのは多分、妻じゃないかと思います。「私みたいに苦しむ人を減らしてほしい」という妻の言葉に背中を押されて連載を始めた経緯もあります。妻はゲラの段階から何十回となく通読して、本になったら感慨深く眺めながら何度も最初っから最後まで一日の半分以上読んでいるんじゃないかと思うぐらいです。同じ本を擦り切れるまで読むのは最近の傾向としてはあったんです。認知症になると内容を忘れるからということもあるんでしょうけど、もしかすると何度読んでも初めて読んでいるような感じなのかもしれないですね。同僚からも好意的な反応が多く、後輩の女性記者から「最後のところ、読んで泣きました」という電話がありました。「お前がこんな状況だって知らなかったよ」という声もよく聞きます。
──この20年を振り返ったとき、特に苦しかったのはいつごろですか。
時期でいうと二つあって、一つは精神科を本人が受けようとしなかった最初の5年間、受診自体が大きな壁だった時期です。もう一つは断酒するまでの最後の2年間ですね。どちらもまったく希望が見いだせなかった。最後の2年間は冷静に考えると精神科医療、特に依存症医療の限界という課題もあると思いますが、どこも引き受け手がなかったんです。一般の精神科では「飲酒の依存症がかなり進行しているから」ということで診てくれない。一方、依存症の専門医の対応は、本人が頑張ってお酒をやめて治療プログラムなどに足を運ばないと基本的にはサポートがないんですね。内科も「お酒を飲める体にして帰すだけになるので、もう診ません」という対応ばかり。このまま痩せ衰えて死んでいくんだろうかというのが最後の2年でした。そこから予想外の認知症がわかって治療の方向が変わり、今に至るのですが、あのままだったら今ごろ生きていませんでしたね。




































