ベテラン木久扇は毎日出演する訳ではないらしい。今日は数少ない出番の日なので、「木久扇師匠目当てのお客さんがいるんだよ」とスタッフの男衆が教えてくれた。
「テレビの『笑点』を昨年卒業しました。55年もやりました。もうあの人たちの顔を見ることはない。ほっとしました。私、5人の司会者を送っております。談志4年、三波伸介13年、円楽23年……」
「談志の選挙第一声、錦糸町で小噺をやった。『今から俺が面白いこというから、笑った人は1票入れてくれ』って。犬の喧嘩で、足が短く胴が長く口が出っ張った犬が勝った。『あの犬、尻尾を切って白く塗る前はワニだったんです』って、面白いんだけど、票には結びつかないの」
最後は、「バイデン大統領のモノマネです」とヨタヨタ歩きで退場。送りのお囃子が「星条旗よ永遠なれ」だった。
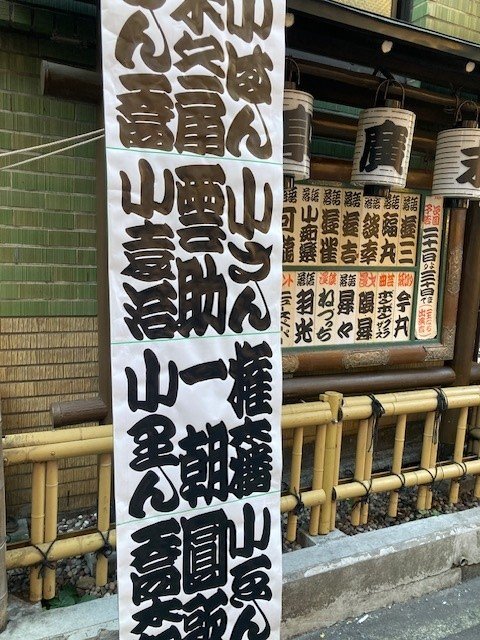
さりげない描写に「時代」が浮かび上がる
ひざがわりの小菊は、いつもの都々逸はやらず、「もしもあたしがウグイスならば、春風がそよそよと〜」なんて春めく歌ばかり歌って、柔らかくトリの高座に繋いだ。
「1月16日といえば、昔は薮入り。昼は初閻魔。新宿なら太宗寺ですな」
おや、小満んの演目は「藪入り」かなと思ったら、今度は人力俥の蘊蓄が始まった。
「明治2年に人力俥ができた。大正14年の箱根駅伝で、俥夫が替え玉で出て5人抜きした。何でばれたかというと、抜き去る時に「アラヨッ」と言ったから。『韋駄天俥夫、山田某』と新聞記事が残っています」
蘊蓄の後は、「朝帰り行く時ほどの知恵も出ず」と古川柳を呟いて、スッと「干物箱」に入った。
道楽のために家の二階に軟禁状態の若旦那・銀之助。今日は薮入りで店の者がいない。「湯屋に行ってもいいが、1時間で帰ってこい」と大旦那に釘を刺される。
吉原へ向かう俥が、若旦那を「アラヨッ」と追い抜いていく。こんな掛け声を聞いたら、馴染みの女に会いたくなった。と、ここで、まくらの人力俥の話に結びつくのか。
博識を気取るでもなく、自分の勉強ぶりをひけらかすでもなく、ごくごく自然に、幕末明治大正の粋な男の生活実感を教えてくれる。桑の箪笥、長火鉢、鉄瓶などの、昔懐かしい小物のさりげない描写に「時代」が浮かび上がる。
こんな隠居が近所にいたら、「道灌」や「一目上がり」などの寄席の定番より、一段上の落語ができそうだなどと思っているうちに、若旦那の部屋で籠城する善公のドタバタで、あっけなく噺の幕が閉じた。
藪入りも過ぎ、長かった寄席の正月がもうすぐ終わる。






































