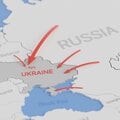「イエーイ。これであいつらは…」
昨年11月には、自爆ドローンでロシア軍を攻撃する様子を取材した。ウクライナ軍の拠点は、何の変哲もない農家の地下室にあった。
兵士はコントローラ―についたジョイスティックを動かし、自爆ドローンを操縦する。ロシア兵が潜んでいる3キロ先の地表をなめるように、高度約3メートルを飛行する。ドローンから見る映像は、地面の小石がわかるほど鮮明だという。それが突然、映像が乱れ、途切れることがある。
「ロシア軍のジャミング(電波妨害)です。すぐ電波の周波数を切り替える。すると、映像が復活する。ドローンを操縦する兵士が緊張するのはそのときくらいです」
ドローンからの映像に、地面の穴が現れた。ロシア軍の塹壕だ。兵士はジョイスティックを慎重に操作してドローンを穴の中に潜り込ませる。画面が暗転した瞬間、兵士の歓声が上がった。
「イエーイ。これであいつらはあの世へいったぜ!」
ドローンの羽音がトラウマ
横田さんはこう話す。
「彼らは軽口をたたきながら、前線でそんな任務を延々と繰り返すんです」
横田さん自身も、「笑い」を交えながら取材してきた。
「そうしないと、どんどん自分が壊れていくのを感じる」
そうして過ごす戦場での緊張感と、帰国して気持ちが緩んだときの落差は「大きい」という。
「日本に戻ると、それまで緊張感でなんとかもっていた体が変調をきたして、吐いたり、下痢をしたりします」
ドローンの音を聞くと、今でも戦場の記憶がよみがえるという。
「あのブーンという音は、本当にトラウマです。心臓の鼓動が速くなって、気分が悪くなる」
「証拠写真」を残す
2年半前に横田さんを取材した際、「ウクライナの取材は嫌だ。相手がロシア兵では危なすぎる」と語っていた。それなのになぜ、7回も通うことになったのか。
「兵士たちがとても親日的なんです。最初はたまたまそういう人に出会ったのかと思っていたら、違った」
ウクライナの人々は日露戦争や北方領土問題についてよく知っているという。「日本も領土の一部をロシアに占領されている。しかも、中国や北朝鮮にも近い。日本のほうが大変じゃないか」と、逆に心配してくれる人までいた。日本の政府や民間企業・団体がさまざまな物資や資金をウクライナに提供していることについても、とても感謝されたという。
「これまでさまざまな戦場を取材してきましたが、ウクライナのような国は初めてです」
横田さんの立ち位置はドライだ。「ぼくに使命感はない。需要があるから戦争を取材する」と言い切る。一方で、全く金にならないが、ウクライナ市民の虐殺された遺体を検視写真のように撮影する。
「将来、『ロシア軍による虐殺はなかった』なんて、言い出すやつが現れるかもしれない。だから、状況をノートに書きとめ、証拠写真を残すんです」
(AERA編集部・米倉昭仁)
こちらの記事もおすすめ 爆撃で「右手を失った息子」母が隠す父の死 ウクライナの施設に収容されるロシア人のリアル