「この先、お墓を維持管理する子どもがいない」「子どもに負担をかけたくない」と、「墓じまい」をする人もいる。継承を前提としない共同墓などに遺骨を改葬するか、散骨するなどして、先祖のお墓を片付ける場合もある。
しかし墓石の撤去、遺骨の移動など、改葬や墓じまいにかかる費用は数十万円から数百万円と経済的負担は小さくない。また、お墓を引っ越すことを菩提寺に申し出たところ、「法外な離檀料を請求された」というトラブルが全国の消費生活センターに寄せられている。その結果、放置された無縁墓が増えるという悪循環が生まれている。
こうしたさまざまな問題の背景には、社会の変容がある。高齢世帯の核家族化が進み、子どもや孫と離れて暮らす高齢者が主流となっている。また特に2000年以降、死亡年齢の高齢化が進んでいる。
90歳以上で亡くなり、死後20年以上経過すると、遺族の高齢化も進む。一緒に暮らしたことのない孫世代は、祖父母の墓参や年忌法要をしない可能性が大きい。生まれ育った場所に先祖のお墓がない人が増えると、墓参にかかる経済的、時間的負担は小さくないこともある。前述のように、孫世代は祖父母を「親戚」だと思っているのだから、90歳以上で亡くなった祖父母の三十三回忌を主宰するとは思えない。
そもそも50歳時未婚率が上昇し、遺族がいない死者も増えている。現にここ20年ほどの間に、引き取り手がおらず、無縁納骨堂に安置される遺骨が全国で増加している。日本では、死後、火葬をしたり、お墓に納骨したりする人がいない場合、自治体が遺族の代わりにおこなわなければならないことになっている。
自治体が引き受けた遺骨が全国で最も多い大阪市では、2022年には3149柱を市設霊園の無縁堂に安置した。これは、大阪市内で亡くなった人の9・2%にあたる。言い換えると、遺骨の引き取り手がいない死者は、10人に1人もいることになる。1990年には無縁堂に安置された遺骨は336柱だったので、この30年間で10倍近くにも増えている。
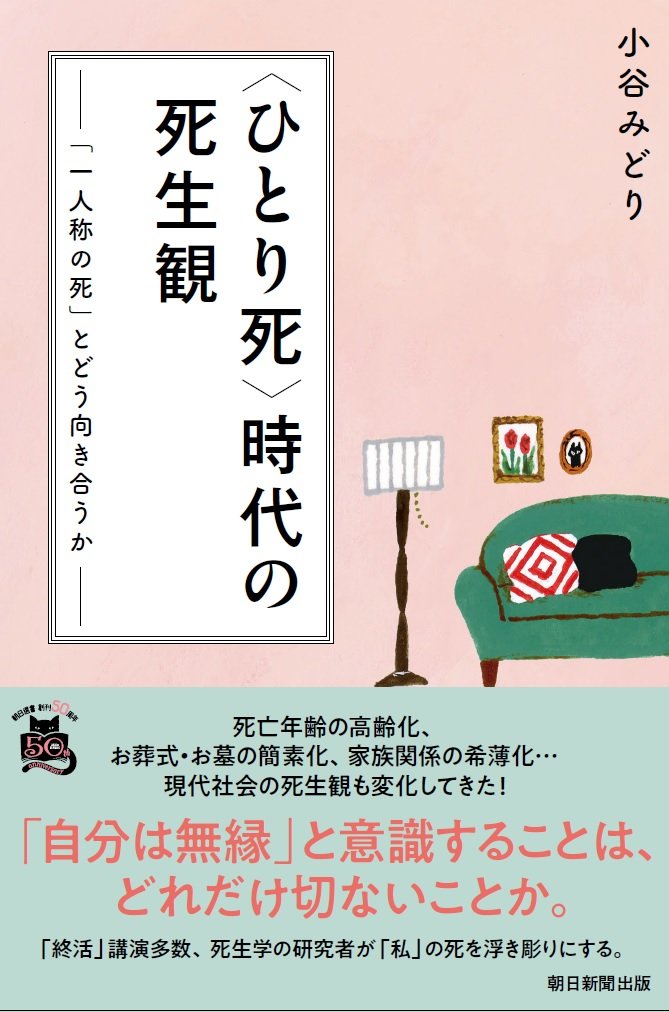
※朝日選書『〈ひとり死〉時代の死生観 「一人称の死」とどう向き合うか』(朝日新聞出版)から一部抜粋
こちらの記事もおすすめ ライフプランに「死」がない 『〈ひとり死〉時代の死生観』著の死生学者が30年前に感じた違和感








































