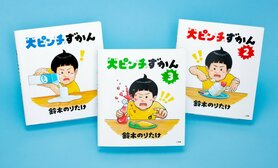ミスター武士道:幕末の動乱もそうですし、信長の死後の混乱もそうだと思うんですけど、やっぱり乱世の中で、日本古来の朝廷の持っている権威みたいなものを使いたくなるというのは、いつの時代でもあることなのかなと思いました。室町時代の政元も、そう考えたのだと思うと腑に落ちますね。お公家さんから養子を取ることも、すごく理にかなっているなと。
私のような現代の戦国時代好きからすると、武士ばかりに注目がいって、朝廷の存在というのはないがしろにしてしまいがちです。今の研究では否定されていますが、信長が自ら天皇になろうとする場面がドラマで描かれたりするくらい、朝廷がないがしろにされているイメージがありますけど、当時の人の感覚としては朝廷の権威は軽んじられない。直接戦闘するわけではもちろん無いんでしょうけれど、やっぱりすごく大きなものだったのだなというのは改めて思いました。
古野:おっしゃる通りだなと思います。先ほど挙げていただいた秀吉もそうですし、それから室町幕府の3代目の将軍義満も、太政大臣になった後にそれを辞めてさらにその上を目指すといったことを考えたりするわけですよね。とはいえ実際に天皇にはなれないわけです。
室町末期や戦国時代のような不安定な時代だからこそ、逆にそういう権威のようなものに頼らざるを得ないというのはあるんだろうなと思います。
それから室町時代のような昔の人たちは、問題が起こった時に解決しようとする時の最終的な手段として、「神慮」といって、神様の配慮というようなところに委ねることがよくあります。室町幕府の6代目の将軍を決める時も、くじ引きで決めてしまいました。あれは細工があったと言われていますが、建前上は「神様の意志」によって義教が選ばれたという体裁をとるわけです。神の意志ですから、それが出されてしまうと、もう誰も文句を言えない。
そして神のような存在として現実世界において体現しているのが天皇や、それを動かしている公家の世界でもあるので、そういったところに最終的な判断を委ねようとするような考え方というのは、恐らく中世を通じてずっと存続していたんだろうと思いますし、もっと言えば幕末まで影響を及ぼしていたのだろうと思います。
ミスター武士道:まさに「神慮」のような超常的なもの、理屈で説明できないようなものに対する当時の人達の感覚として『オカルト武将』で面白いなと思ったのが、政元が暗殺された時に、暗殺者たちが政元の足の裏を執拗に傷つけて、万が一蘇ったときに歩けないようにしたという点でした。