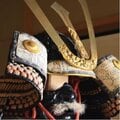室町時代から戦国時代に切り替わったタイミングはいつなのか。日本史の教科書には、「応仁の乱終結」から「織田信長の上洛」までの約100年間に関する記述が薄いものが多い。
室町末期に詳しい古野貢教授は、著書『オカルト武将・細川政元』の中で、明応の政変が戦国時代の始動に果たした役割について言及している。
新刊「『オカルト武将・細川政元 ――室町を戦国に変えた「ポスト応仁の乱の覇者」』(朝日新書)」から一部を抜粋して解説する。
* * *
応仁の乱をきっかけに室町幕府の政治体制は崩壊したと書きました。それは「中央政府ですべてが解決できなくなり、地方の事柄は地方でないと解決できない」ことがはっきりしたためです。では幕府の力がすっかりなくなったのかと言えばそうではありません。先ほども書いたとおり、義昭の時代まで幕府は残っていたわけです。
応仁の乱後も、しばらくは将軍と室町幕府の影響力に実効性は残っていました。京都を中心に、西は現在の岡山や広島あたり。東は富山や名古屋あたり。これに鎌倉府を加えた関東に広がる範囲で室町幕府と足利将軍の権威と機能は存続し続けていました。そのため、地方のあちこちで自力による問題解決はたしかに始まっているのですが、そこで決着がつかなかった場合に、現代で言うところのあたかも最高裁判所に判決を求めるように、幕府と将軍に持ち込んでなんとかしてもらおうという動きはあったのです。
しかし、政元の起こした明応の政変によって将軍と幕府の権威が著しく下落したため、地方の諸勢力は「将軍の決裁は役に立たない」とその価値を認めなくなる時代がやってきます。政元が実行した明応の政変は時代を進め、戦国時代に突入させるのに大きな役割を果たしました。一番大きいのは、「百数十年にわたって維持されてきた既存の政治的ルールを壊し、タブーを乗り越える前例を作ったこと」でしょう。
室町幕府においては、頂点に足利将軍がいて、その下に斯波・細川・畠山の三氏(三管領家)が就く管領職があり、有力武家が任命される守護がいて、という現代とは異なる序列・階級のある社会でした。そのような、誰もが当たり前だと信じていた社会のあり方を、政元は「乗り越えてもよい」と示してしまいました。
その結果として各地に戦国大名が現れ、たとえば今川氏などは「今川仮名目録」という独自の法度(法律)を作り、「以後はこの法度で統治します」と宣言するわけです。もともと室町幕府には幕府法ともいえる法律があり、これに基づいて裁判をしていくわけですが、その中央のやり方を無視して独自のやり方を行っていく。これがまさに戦国時代のあり方なのです。
戦国時代はこのようにして始まったと考えられ、良くも悪くも細川政元が果たした役割は非常に大きかったと言わざるを得ません。
政元の下剋上には中途半端だったという指摘がついて回ります。将軍を追放しましたが、将軍がいて幕府があってというフォーマット自体は残したからです。彼に続く長慶や信長も同じように幕府の仕組みは壊さなかったので、まとめて改革者として不十分だったと言ってしまうこともできるでしょう。
とはいえ、新しいフォーマットが作られる、変化のための段階を踏んでいたとも言えます。家臣が将軍を追放し、新たな人物にすげ替えるには、新しい政権構想とそれを実現するための準備が必要なわけです。この点では新しい将軍を据える構想が欠けていた嘉吉の乱とも、戦争の先に新たな構想を見出せず、延々続いた応仁の乱とも全く違います。
政元は政権構想的なものを持ったうえで、一定程度の実現可能性がある計画に基づいて具体的に動いたわけです。世の中を変え得る動きを見せたことが、時代の変化の大きな起点として評価できる点であると思います。
『オカルト武将・細川政元』では、政元が織田信長よりも先に実行した「延暦寺焼き討ち」、将軍追放のクーデターにおける日野富子との交渉など、応仁の乱から信長上洛までの“激動の100年”を解説しています。