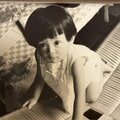そしてなんといってもこの辺りの名物の「蒸し寿司」が絶品。酢飯の上にそぼろになった甘いお揚げや薄切り蓮根、干し椎茸や菱形に抜かれた薄焼きのたまごなどがのっているものをふんわり蒸して、春慶塗のお重に入って供されます。なんとも歴史と文化を感じるお料理の数々に舌鼓を打つ野生のトーコ。すでに幸せの極地。
さて、そこへ祭りの獅子舞がやってきて家の前で門付けしていきます。そうこうするうちに烏帽子を被り装束をつけた方たちがやってきて、家の中で雅楽の横笛、竜笛、笙の笛を演奏して行かれました……。なんなんだ?? ここは時代が遡っている?という気分になっていると、まだ明るい夕方の町で子供たちの鶏闘楽という踊りの行列が。家の前の通りを鮮やかな衣装をつけて鉦(かね)と太鼓、笛の音に合わせて踊りながら過ぎていきます。しんがりには裃(かみしも)をつけたお役の方が歩いていきます。
ねえ、ほんとに私、タイムマシーンに乗っちゃった?
夜の帳が下りる頃、祭りのクライマックスに向けて町が動き始めます。
飛騨神岡祭は、三社の例祭の総称です。一番大きな「大津神社」の山の上り口前の広場に人が集まり、日中は町の中を練り歩いていた獅子たちや鶏闘楽の行列が集まり、順に群衆の真ん中の広場で舞いや踊りを披露し、それが終わるとそれぞれの社中が順に神社へと上がっていきます。
笛や太鼓だけでなく神岡祭では雅楽が演奏されます。そして驚くべきことに奉納される雅楽はすべて地元の方たちが演奏しているのです。
録音の音源など、全く使われない。この町の人たちはみな横笛が吹けるのか? 目の前で信じられないような平安絵巻のような光景が次々に繰り広げられるのです。白拍子のようなみやびな装束をまとい烏帽子をいただいた20人近い女性たちが朱色の緋毛氈(ひもうせん)の上に正座し横笛を吹く姿は圧巻でした。
この頃には、私の心はすっかり神岡の町に溶け込んでいました。