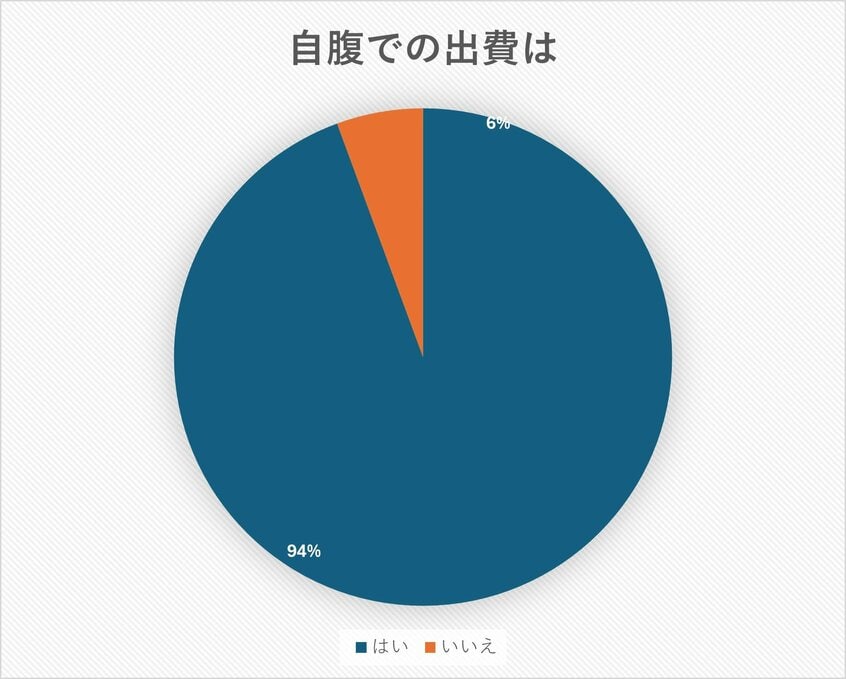
保護者のクレームに耐えられない
保護者が介入するのは、部活動だけではない。生徒同士でトラブルが起こっても、保護者が乗り出してくる。ほぼ、代理戦争だ。
「短い人だと、『私には無理です』とすぐに辞めてしまうんです」
そう語るのは、ある私立の中高一貫校で高等部の部活顧問を長年務めてきたサチコさん(仮名、50代)だ。公立とは異なり、教員の働き方改革が進む私立では顧問を断れる学校が少なくない。その反動で、同校の中等部の部活顧問は長続きせず、「2、3年ごとに変わってしまう」(サチコさん)。
原因は、部活動にまつわる生徒のトラブルだ。たとえそれが些細なことであっても、保護者は、「いったい、どうなっているんだ」と、顧問に抗議するのだ。
「経験の浅い顧問には保護者も文句を言いやすいのか、強く責め立ててくる。顧問が精神的に参ってしまうんです」(同)
たとえば、部室内で私物が紛失したとする。
「保護者が『誰かに盗まれた』と言ってくる。きちんと捜せば、大抵見つかるんですよ。でも、はなから『盗難』と決めつける保護者がいるんです」
「友人に貸した金を返してもらえない」といったトラブルもある。最近増えているのはスマホにまつわるトラブルだ。
保護者によっては、子どものスマホ使用に制限をかけている。制限のないスマホを友人から借りてゲームをし、もしも課金をすれば、当然トラブルになる。
「女子部員の保護者はすぐに『いじめだ』と言ってくるし、対応が本当に大変です。高校に入るとだいぶ落ち着く印象がありますが、中学校の部活はそういうことも起こってくるんです」(同)
記者の子ども時代、子ども同士のトラブルは、よほど悪質なケースを除き、顧問が注意すれば収まったように思う。
現代は、そうは保護者が卸さない。保護者の過剰な介入は、部活動の不幸な歪みにもなっているのだ。
(AERA編集部・米倉昭仁)
こちらの記事もおすすめ 【ギリギリの部活~1回目】子どもの部活動「フルサポート」に保護者が悲鳴「野球部には入らないで」 「送迎」「引率」「お茶係」の重圧



































