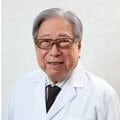死亡年齢の高齢化、葬式・墓の簡素化、家族関係の希薄化……社会の変化とともに、死を取り巻く環境も大きく変化してきました。30年前、生命保険会社が顧客に提示するライフプラン表は、「老後」で終わっていて、「死」というライフイベントを含めるという発想はなかったといいます。
この30年間、死生学の研究をしてきたシニア生活文化研究所代表理事の小谷みどりさんが、現代社会の「死」の捉え方を浮き彫りにする新刊、朝日選書『〈ひとり死〉時代の死生観』(朝日新聞出版)を発刊しました。同書から「序章」を抜粋してお届けします。
【写真】小谷みどり氏の最新刊『〈ひとり死〉時代の死生観』はこちら
* * *
私が、人の生き死にをテーマにした研究をはじめて、30年がたつ。大学院を修了し、生活設計関連のテーマを自主研究する第一生命のシンクタンクに入社したものの、そもそも研究者志望だったわけでもない私は、何を研究するべきか、悩んだあげく、「お墓についての意識を調査しよう」と思い立った。
しかし、研究所の上司たちは、「誰とお墓に入りたいかなんて考える人はいない」「子孫は先祖のお墓に入ることが当たり前に決まっている!」などと、お墓のあり方や意識を研究する意義や理由がわからないと、このテーマに猛反対した。
なぜ私が、お墓や死について研究してみようと思ったのか。
1つ目は、「特に研究したいことがないのだから、どうせなら、大勢の人に関係のあるテーマにしよう」と考えたことにある。みんなに共通するライフイベントは、「生まれた」ということと「死ぬ」ということしかないのだが、「生まれた」のは本人の意思ではないため、「死」こそが、すべての人が直面することだと気づいたのだ。仏教では「生老病死」を四苦というが、生まれてすぐ亡くなり「病老」がない子どももいれば、「老」を知らずに若くして病死する人もいる。どんな人生であっても、死なない人はいない以上、この世の人生は死で終わることを、私たちはもっと意識すべきではないかと考えた。
しかし30年前、生命保険会社が顧客に提示するライフプラン表(これからの人生で、いつどのタイミングでどの位のお金がかかるのか、平均費用を示した図)は、「老後」で終わっていた。