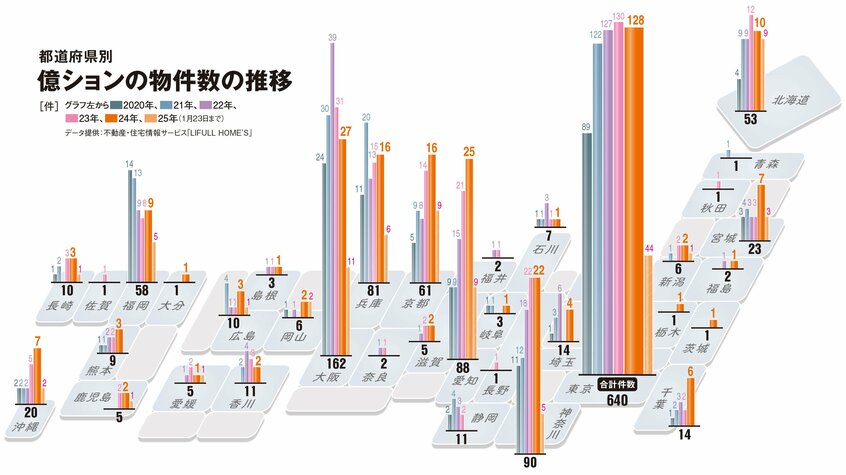
最上階の一部の戸数にとどまるとはいえ、地方都市のタワマンまで億ションと化した背景には、世界的なインフレの進行に伴う資材価格の高騰と、空前の人手不足による人件費負担の増大がある。中山さんは補足する。
「国は働き方改革の一環として残業時間の上限規制を定めましたが、建設業のような労働集約型の企業に対しては5年間の猶予措置を設けていました。その期限が訪れ、昨年4月から残業時間の上限規制が適用されたことで、人手不足がいっそう深刻化しているのです」
相続対策としても有効
地方の富裕層がローカル億ションに熱い視線を注ぐのは、相続対策としても有効だからだ。
「不動産にかかる相続税を計算する際、その価値は実勢価格ではなく、路線価をもとに評価されます。一般的に路線価は実勢価格よりも安く、たとえば1億円の物件であっても6千万円程度の評価額になり、資産を現預金などで保有しているケースよりも大幅な節税(税負担軽減)が可能です」(中山さん)
しかも、タワマンは1棟に数多くの戸数が入っている。そのため、1戸当たりの敷地該当面積が相対的に小さくなり、同面積の敷地に立つ低層マンションと比べて、土地部分の相続税評価額がかなり低くなる。
一方、タワマンは高層階ほど実勢価格が高くなる傾向にある。相続税評価額が割安に(=税負担が軽く)なるうえ、実勢価格が割高に(=売却時も有利に)なるのだ。この乖離現象に目をつけ、首都圏にタワマンが続々と建ち始めた頃から富裕層の間でタワマン節税がブーム化した。
バブル再来にあらず
そこで、国はタワマンに対する相続税評価方法を見直し、昨年1月1日以降に発生した相続においては、一昨年末までのような大幅節税は難しくなった。とはいえ、依然としてタワマンが相続税負担を抑える有効策であることに変わりはない。だからこそ、地方の富裕層がローカル億ションに群がっているのだ。
ディベロッパーがローカル億ションの建設地として白羽の矢を立てるのは、観光地として名高い地域や、大規模プロジェクトが進められている地域の県庁所在地だ。前者の好例が沖縄で、後者については熊本が筆頭に挙げられる。長嶋さんはこう語る。



































