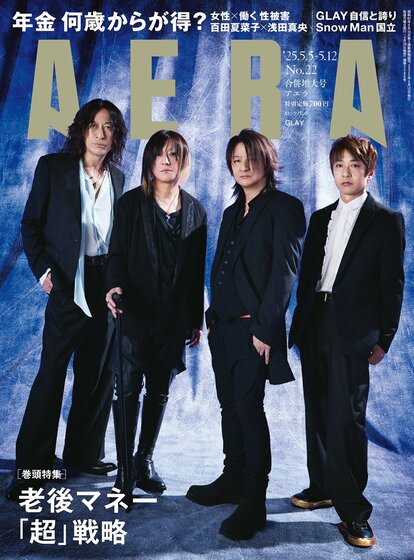地震、津波、噴火、台風、洪水……日本は驚くほど自然災害が多い。各時代の日本人がその中をどう生きぬいてきたか。“自然大災害(大変)が出てくる文学”を通して描いた一冊。
『方丈記』にある元暦2年の地震。東日本大震災まで国内最大だった宝永地震、1カ月半後の富士山宝永大噴火を書いた新井白石『折たく柴の記』。噴火の降砂に苦しむ農民のために奮戦する関東郡代を描く新田次郎『怒る富士』など、古代から現代まで災害の絡む27章からなる。
谷崎潤一郎『細雪』に出てくる阪神大水害は近代文学でも災害を描いた屈指の場面として知られるが、じつは同水害は戦時下の報道管制で広く国民に知らされなかった。それを描く谷崎に、著者は“時局”への抵抗を見ている。災害から眺めてみると、日本文学の別な姿が見えてくるのだ。
明治と昭和の三陸地震大津波の間を生きた宮澤賢治の姿もある。東日本大震災から5年の今年、まさに読むに相応しい本だろう。自然災害と日本文学を結んで書かれたものが今までなかったという事実にも、驚かされる。
※週刊朝日 2016年3月4日号