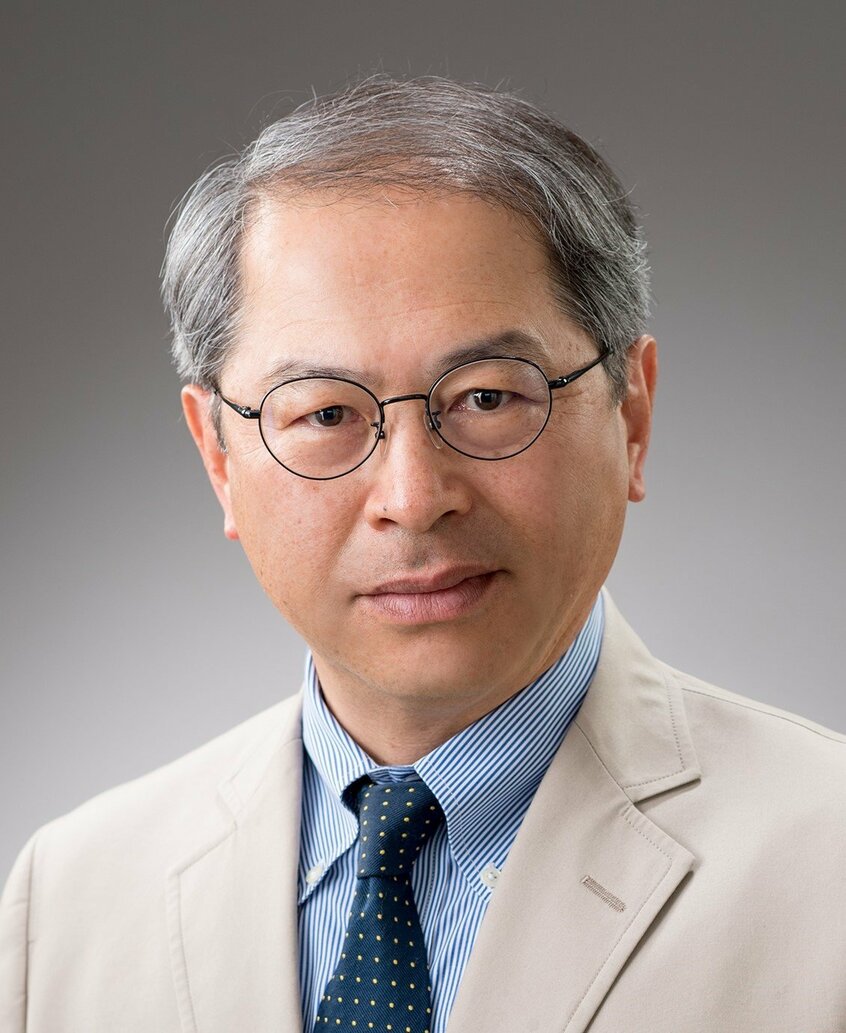
米国ニューヨーク市では相次ぐ自然災害のリスクを低減するため、現在20%強の「樹冠被覆率」を2035年までに少なくとも30%に引き上げる官民プロジェクトが進行している。樹冠被覆率とは、土地の面積に対して枝や葉が茂っている部分(樹冠)が占める割合。いわば、「緑の日傘」を広げる運動だ。
パリやロンドンなど欧州の都市で顕著なのは、ビルの屋上や壁面の緑化推進だという。伝統的な景観や街並みの保全を重視する欧州では、日本のように大規模再開発に伴う公開空地を活用して緑を増やすのは困難なためだ。
背景には、気候変動対策や生物多様性の保全、都市住民の徒歩圏内での生活環境の向上といった環境的側面に加え、中心市街地の空き地対策の側面もあるという。
グリーン戦略で活力再生、空き地対策でも注目
新型コロナのパンデミックを契機に在宅勤務が進んだ結果、都心のビルに空きテナントが増加したり、産業構造の変化により人口が大幅減少し、工場跡地が放置されたりすることによる治安悪化が、世界の都市で問題になっている。そのソリューションの一つとして、「緑化」が位置づけられているのだ。
有名なのは財政破綻した米国ミシガン州のデトロイトの事例。空き地や工場跡地を緑化して、都市の活力を再生する「グリーン戦略」を採用している。これは地方を中心に人口減少が続く日本もよそ事ではない、と横張教授は言う。
「日本の緑化はこれまで環境的側面が主でしたが、今後は中心市街地の空き地対策としてもクローズアップされると思います」
緑化は都市の風景の荒廃を修復するだけでなく、人心の荒廃を防ぎ、防犯効果を高める側面も期待される。
一方、土地の少ないシンガポールでは2030年までに食料自給率を30%に引き上げる目標達成のため、野菜や果物を栽培する屋上農園の設置を政府が後押ししている。地球規模の気候変動や世界各地で起きる紛争などによって食料品の輸入が一層困難になるのを見越した対応だという。
また、建築技術の進歩と相まって、木材の使用比率が高い「木造ビル」の建設の動きも国内外の都市で進んでいる。これもCO2対策や林業振興を兼ねた政府や自治体の政策誘導と連動して注目されている。横張教授はこう強調する。
「世界情勢が流動化するなか、日本も農林業の振興も含め、緑が持つポテンシャルを最大限活用するさまざまな仕組みづくりが必要です」
(編集部・渡辺豪)
※AERA 2023年11月27日号







































