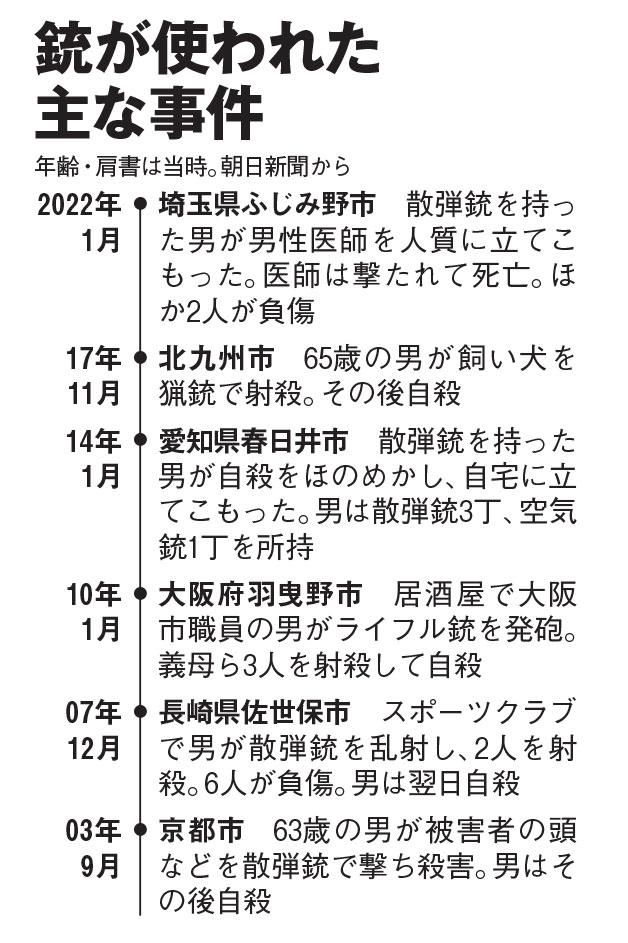
「狩猟免許や所持許可のハードルを高くすることで一定の効果はあるかもしれません。ですが、容疑者がナイフを使ったように、誰かに危害を加えたい人にとって凶器は銃である必要はありません」
福田教授によれば、アメリカなど銃が普及する国では、犯罪抑止には中長期的な心理的ケアが必要であるとの認識が進んでいるという。
「免許を取った時点では精神的に問題がなくても、その後バランスを崩すこともある。そのときにケアできる体制が周りにあるかどうかが重要です」
不安定な状態から過激化する人を出さないためには、コミュニティーでの見守りが不可欠だ。地元紙「信濃毎日新聞」によると、青木容疑者は精神に不調をきたし、都内の大学を中退。病院の受診を勧める両親に「俺は正常だ」と拒否したこともあると報じられている。
地元に戻った青木容疑者は狩猟免許を取得。長野県の北信猟友会に所属していたが、他の会員との交流はほとんどなかったという。
猟友会関係者は言葉少なにこう語る。
「事件の内容が明るみに出るにつれ、あまりのひどさに言葉がありません。ただ、こういう人が猟友会メンバーだったことを重く受け止めています」
林業や農業に携わる人にとって、猟銃は切り離すことができない仕事道具でもある。形だけの規制ではない対策が急務だ。
(編集部・福井しほ)
※AERA 2023年6月12日号







































